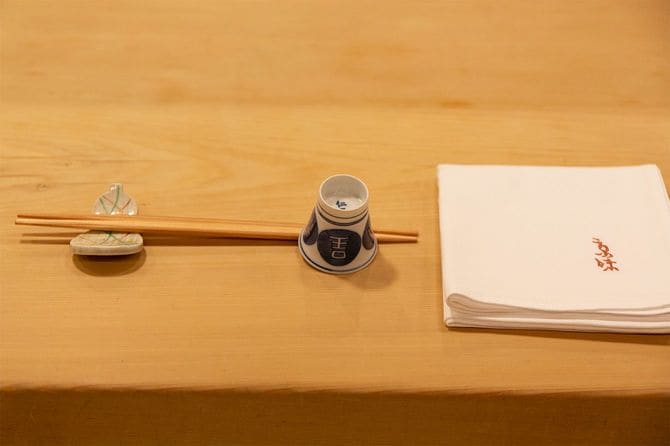※本稿は、野地秩嘉『京味物語』(光文社)の一部を再編集したものです。
どの瞬間に塩を振るかで味は変わる
「京味はおいしい」「西さんの料理は特別だ」とよく言われる。確かに、今、世界の和食店で彼以上の技術を持つ人はいない。わたしは印象や思い付きで判断しているのではない。客観的に、他の料理人ができないことを彼はやっている。
たとえば、味を調えるタイミングだ。京味のレシピを伝える本は何冊かある。もちろん、西健一郎が監修している。ただし、レシピ本には宿命がある。どうしても書くことのできない点がある。それが調味のタイミングだ。
塩を振る、砂糖を煮汁に入れる。レシピには何グラムと書いてある。しかし、量は対象の大きさ、鮮度、料理をする季節、食べる相手によって微妙に違ってくる。また、どの瞬間に塩を振るかで味は変わる。
そして調味のタイミングは素材の別や個体の量によって変わってくるから、文章にするとだらだらと長くなる。読んでもわかりにくい。動画でも伝わりにくい。
しかし、一流の料理人はすべての条件の違いを踏まえて、一瞬で調味できる。この材料なら、これくらいの塩を全体に振る、あるいはこの部分にだけ載せることがわかる。
レシピにはそこまで細かいことは書いていない。西は何十年もの間、多くの種類の野菜、鮮魚などを調理してきているから、それができる。
刺身ふた切れを差し出して…
調味するタイミングについて、話を聞いていた時のことだ。
「食べてみますか?」
目の前で鯛を切り、刺身をふた切れ作った。両方に塩をほんの少しずつ振った。
そして、ひとつをすぐに食べろと言った。もうひとつはやや時間をおいてから口に入れろと……。
時間をおいたと言っても1分くらいのもので、せいぜい2分だった。刺身をカウンターの客に出して、客がひと切れ目を口に運ぶくらいの時間だった。
すぐに食べた方は塩気を感じた。二番目に食べた方は甘みを感じた。大きな違いだった。二番目に口に入れた刺身は最初のそれよりも甘みを引き出してあった。
西は何も話さなかったけれど、時間が甘みを引き出す。そして、甘みを引き出すような塩の振り方を彼はしていた。
塩でも醤油でも砂糖でもいいけれど、調味料は入れてから食べるまでの時間で素材の味を変えてしまう。そのタイミングを文字や動画で伝えることは至難の業だ。京味のレシピ本を読んでも、その技を手に入れることはできない。