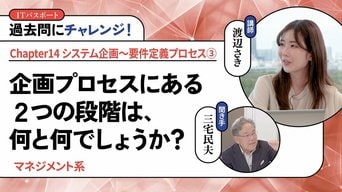日本経済の成長力が弱くなった現在、次のリーディング・インダストリーを見つけるのは難しい。一定の条件が整えば、化学産業には、その役割を担う可能性が大いにある、と筆者は説く。
「知る」と「解る」の違いはどこにあるのか
近時マスコミなどで、何度か繰り返される政治家の出処進退の判断の是非。外から言うかぎりは、どうとでも言える。だが、内に入り事情を深く知ると、人と人との関係が絡み、判断はことのほか難しい。誰しも、出処進退や仕事の踏ん切りのつけ方には悩むものだ。今回は、阿部謹也氏の「解るとは何か」そして「何が解れば解ったことになるのか」についての議論を手がかりに、出処進退に絡んで、「仕事の成否を自分に問う」こと、〈大問題〉を立てることの大事さを考えたい。氏は、ヨーロッパ中世史の研究で知られ、一橋大学の学長を務められた碩学である。
さて、阿部氏の著作の一つに、『自分のなかに歴史をよむ』(筑摩書房、1988年)がある。そこでは、「解る」ということにまつわる自身の経験が紹介される。
一つは、氏が学生時代に卒業論文のテーマを選ぶために、その後、氏の先生となる上原専禄先生に相談にいかれたときの経験である。そのとき上原先生からは、「どんな問題を選んでもよいが、それをやらなければ生きてはいけない、そんな問題を選びなさい」と言われたという。たかが卒業論文と言うなかれ、である。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント