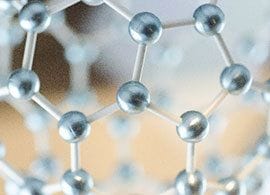がんは不治の病ではない。研究の現場を訪ね歩くと、そう感じる。アプローチは1つではない。治療法はあらゆる角度から進化している。研究者たちのほとばしる熱意を感じてほしい──。
現在、使われている抗がん剤は次の2つに大別される。
(1)細胞のDNAや分裂システムを破壊して、細胞を殺すもの
(2)細胞の特定の分子に作用して、細胞の増殖を抑えるもの
このうち、(1)は「殺細胞性抗がん剤」と呼ばれる薬で、従来の無差別攻撃型の抗がん剤を指す。一方の(2)は、この10年で急速に研究が進んだ「分子標的薬」のことだ。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント