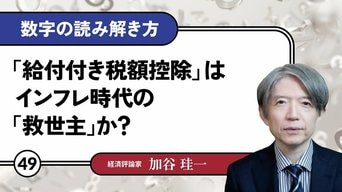普通の人に“擬態”して生きる
灰谷泪さん(仮名・40代)は初めて入社した広告制作会社で、半年の間にmacのキーボードを3台壊した。3台ともコーヒーをこぼしたせいだ。毎日遅刻ギリギリで出社していることや、空気を読めないせいで場違いな言動をしていることを、暗に指摘されることもあった。
小さな広告制作会社にありがちなのは、終電までの残業や徹夜がザラにある、いわゆる“ブラック企業”だが、灰谷さんの勤め先は“過酷な重労働でブラック”なのではなく、“女性の仕事”だった。
「体力はある方だし、汚れ仕事や力仕事だって気にならない。むしろ女性だからと特別扱いはせずに、対等に評価してもらいたかった。何日か家に帰れなくたって、将来の仕事に繋がるなら我慢できる。そう思っていました」
ところが、実際に入社した会社は「男性と同等の仕事」ではなく、「女性の仕事」を任せた。
「電話番、お茶出し、掃除、コピー、資料のクリップ留めなど、ごく一般的に『女性の仕事』とされてきたこと。つまりは、きつくもないし力仕事も求められない代わりに、毎朝愛想良くコーヒーを淹れるとか、流し台のマグカップをこまめに洗っておくとか、そういう気の利かせ方や、空気を読むスキル、何でも気安く頼めるような可愛がられるキャラクターが求められる仕事だったのです。私は見た目に気を使えず、社交辞令もうまく言えないし、受け流せない。愛想も悪くて、気も利きません。不運なことに、私は女性でありながら、『女性の仕事』にまったく適性のない人間でした」
短くて数カ月。長くて3年ほどで転職を重ね、失敗を繰り返しながらも、どうにか空気を読んで、周りの人と同じように振る舞おうと試行錯誤の毎日。灰谷さんは、“普通の人”への“擬態”が達者になればなるほど、「また失敗するのではないか」という不安と、本来の自分を抑圧するストレスが溜まっていった。
そして31歳になった時、やっと理想的な会社への転職に成功。新しい会社の人たちは、灰谷さんを温かく迎え入れてくれた。
「個性を大切にする風土で、社内サークルやSNSでの交流も盛んでした。私はさっそくニックネームで呼ばれ、『趣味は?』『休日何してるの?』と質問攻め。費用は会社持ちのランチミーティングに、使い放題の本格的なコーヒーマシン、休日はバーベキューと、福利厚生やイベントも充実していて、至れり尽くせり。上司は有能で常識人。これまでの会社とは大違いで、徹夜どころか残業もほとんど求められず、指示も丸投げじゃなく、丁寧でわかりやすかったです」
ところが、皮肉にも灰谷さんが会社に行けなくなったのは、その会社に入社して約半年後のことだった。
「仕事中、『私は今、何をやってるんだろう』『なんでこんなことをしてるんだろう』そんな言葉が頭に浮かんで、キーボードを打つ指が動かなくなりました。ブラック企業の社長のご機嫌取りのために資料を作るよりも、よっぽどやり甲斐があるはずの仕事を目の前にして、なぜか私には自分がそれをやる意味がよくわからなくなってしまったのです」