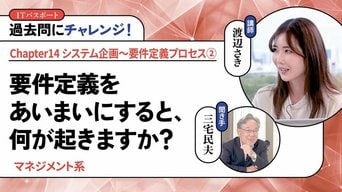厚生労働省によると、2025年3月時点の生活保護の申請件数は、2万2484件(前年同月比867件増加、4.0%増)。生活保護を開始した世帯数は、2万395世帯(同1062世帯増加、5.5%増)。賃金は上がらず、物価が異常に高騰する中、さらに生活保護が必要な人々が増えるのは必至な状況だ。
介護や毒親の取材現場で筆者が以前から気になっていたのは、経済的な困窮者が生活保護を忌避するケースが多いことだった。その背景には、不正受給問題はさることながら、生活保護の仕組みの複雑さや“得体の知れなさ”が影響しているのではないか。そんな問題意識を胸に、かつての生活保護受給者の話を通じて制度の実態を明らかにし、正しく救われる人や機会を増やしていきたい。
「もう死ぬしかないんじゃないかと思うんです」
関東在住の灰谷泪さん(仮名・40代)は約10年前にうつ病を患い失業した。以降、外出恐怖症のような状態になり、アパートに引きこもりがちな生活を送っていた。
しばらくは自分の貯金で生活していたが、それが尽きると、北陸地方に暮らす60代の両親を頼るしかなかった。
それでも、病状はなかなかよくはならなかった。
「どんなに休養を重ねても、散歩や日光浴をしても、自分のせいで親に苦労をかけているという罪悪感と、働けない自分への失望と、『働けないなら生きている価値がない』という認知の歪みはどうにもなりませんでした」
2017年、希死念慮が強まり、睡眠薬を処方してもらうことを目的に、心療内科を受診。しかし医師が処方したのは抗うつ剤のみ。勧められるままに通院するようになると、発達検査を受けることに。結果、ASDとADHDと診断された。
「発達障害の診断を受けたことも、よい面もあれば悪い面もありました。これまで何をやってもうまくいかない理由が発達障害の特性にあったとわかったまではよくても、わかったからといって、それが治せるわけではない。自分が社会に出ても、結局周りの足を引っ張ってしまうだけなのだと思った時、私はどうやって生きていけばいいのかわからなくなってしまったのです」
そんなところへ2019年、上の姉の夫の訃報を聞いたことをきっかけに、精神状態が一気に悪化した。
「上の姉には、まだ小学校低学年と未就学の子どもがいます。義兄が亡くなってしまった今、両親は私より上の姉に支援すべきです。私は自分のような“ごく潰し”が老親のお金を頼って生活している現実に耐えられなくなりました」
そうはいっても灰谷さんは、すぐに就労できるような状態ではない。おまけに当時はコロナ禍が始まったばかりだった。灰谷さんは、心療内科から紹介されて通い始めた発達障害者支援センターの相談員に相談する。
「だから、もう死ぬしかないんじゃないかと思うんです」
泣きながら自分の気持ちを打ち明け、最後に絞り出すように口にすると、担当相談員は真剣な顔で言った。
「灰谷さん、人が働くのって、食べていくためだけじゃないですよ。たとえばですけど、生活保護を受けながら、働ける時だけ働いたっていいじゃないですか」
それを聞いた灰谷さんは、“最後の手段”だと思っていた「生活保護」という言葉が出たことにショックを受けた。
果たして灰谷さんは、「生活保護」を利用したのだろうか。そもそも、なぜうつ病を患ってしまったのか。
その答えは、彼女の生い立ちにあった――。