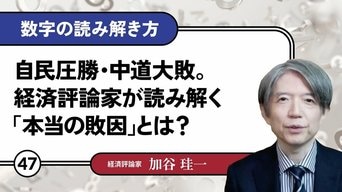敗因は「中道」結成以前の立憲にある
自民党との「政権の選択肢」となり得る「もう一つの国民政党」の一歩手前まで来ながら、衆院選直前の新党結成を経て今回の衆院選で惨敗し、再び「戦後最小の野党第1党」に逆戻りしてしまった中道改革連合(立憲民主党)。選挙直前に新党が誕生したので、党名の書き方に苦慮してしまうが、本稿は基本的に「新党結成より以前の立憲民主党の動き」に敗因を求める方向で進めたい。「立憲」「中道」の混在が読みにくさを感じさせてしまうかもしれないが、ご容赦いただきたい。
さまざまな敗因分析があるが、ここでは筆者が以前よりこの場でも指摘し続けてきた「消費減税」を、改めて取り上げる。政策論を超えて考えるべき、さまざまな論点があると考えるからだ。
そもそもの立憲の「存在意義」とは
①「目指す社会像」はどこへ
最初に考えるべきは「立憲は何のために結党されたのか」ということだ。
立憲は2017年の「希望の党騒動」で当時の民進党(民主党から改称)が、強い改革保守志向を持つ「希望の党」と合流を図った際、排除された枝野幸男氏らが初代代表となり結党した政党だ。排除された議員らの「救命ボート」だったのは確かだが、同時に立憲の結党は、希望の党騒動によって政界が「保守2大政党」に引き寄せられかけたことに抗い「自民党と異なる社会像を掲げた」意義があった。
こう書くと「それが反原発だ」「反安保法制だ」などと言い出す向きもあるが、それは大きく違う。立憲の存在意義は、21世紀に入って以降の自民党が進めてきた「自己責任を強いる社会」ではなく、公助の充実で国民の暮らしの不安を取り除く「支え合う社会」を掲げたことだ。
立憲は結党直後の衆院選で、希望の党を抑え野党第1党となった。「自民党と異なる社会像の対立軸」が明確な政党が、初めて野党第1党になったのだ。立憲は2020年、希望の党から移行した民主党系議員による旧国民民主党の議員の大半や、無所属の元民主党系議員が加わり、新しい「立憲民主党」となったが、綱領に掲げた政治理念や「目指す社会像」は、基本的に旧党のものが堅持された。