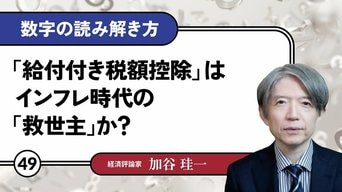なぜイトーヨーカ堂を売却したのか
日本の小売業界はいま、かつてないほどの地殻変動に直面している。
セブン&アイ・ホールディングスは、祖業であるイトーヨーカ堂を手放した。ロフトや赤ちゃん本舗などを含む中間持株会社ヨークHDをベインキャピタルに約8100億円で売却し、自らは35%を再出資する形で、百貨店・GMS(総合スーパー)から撤退したのである。半世紀以上にわたり総合小売の看板を背負ってきたセブン&アイが、その看板を自ら降ろした瞬間だった。グループ再編はこれで完了し、セブン&アイは事業の軸足をコンビニ事業に全面的に集中させる。
ベイン傘下に移ったイトーヨーカ堂は今後、従来のGMS業態から食品スーパー・ドラッグストア事業に経営資源を集中させる方針を打ち出しており、衣料品や住関連商品の部門は別会社に移管して「食」に特化する。総合スーパーから業態転換し、収益性向上を図るこの戦略は、「何でも屋」から「専門特化型」への象徴的な舵切りと言える。
同じ時期、株式市場では異変が起きていた。長年セブン&アイを下回っていたイオンの時価総額が逆転し、流通業の「王者交代」が現実となったのだ。セブン&アイは「高利益×低回転」のモデルで高収益を維持してきたが、重い資産構造と国内成長余地の限界が市場に見透かされた形でもある。
小売業界は「戦国時代」に突入
トップ交代を許したセブン&アイに対し、イオンは総合スーパーから食品スーパー・金融・ヘルス&ウェルネスまで幅広い事業を持ち、潜在成長性への期待感が高まったことも要因だろう。つまり、市場は単なる規模ではなく、構造変革への戦略性を重視しはじめている。
さらに、ディスカウントの雄パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH、旧ドン・キホーテHD)が、国内事業規模でイオンリテールを抜き去ったことも話題となった。ドンキを中心としたディスカウントストア事業と、アピタなど総合スーパー事業を合わせた売上高は、2025年6月期で1兆9000億円台となり、イオン主要子会社のイオンリテール(2025年2月期1兆8777億円)を逆転したのだ。かつては「安売りの異端児」と見られていた存在が、ついに総合小売の牙城を崩しつつある。
いま日本の小売で起きているのは単なる「順位の入れ替え」ではない。総合業態から専門特化型へ、規模の覇者から構造の勝者へと主役が移る大転換期である。表面的な売り上げや店舗数ではなく、ROA(総資産利益率)という「利益の厚み×資産の軽さ」を映す指標が、各社の真の実力を映し出し、勝敗を決しつつあるのだ。
セブン&アイは「祖業切り捨て」という決断で高収益モデルを徹底し、イオンは重い資産の軽量化と事業ポートフォリオ再編に活路を探る。ドン・キホーテのPPIHは中利益×中回転のバランスで拡張を続けている。小売業界は今まさに「戦国時代」に突入しており、ROAを制した者こそが次の覇者となるだろう。