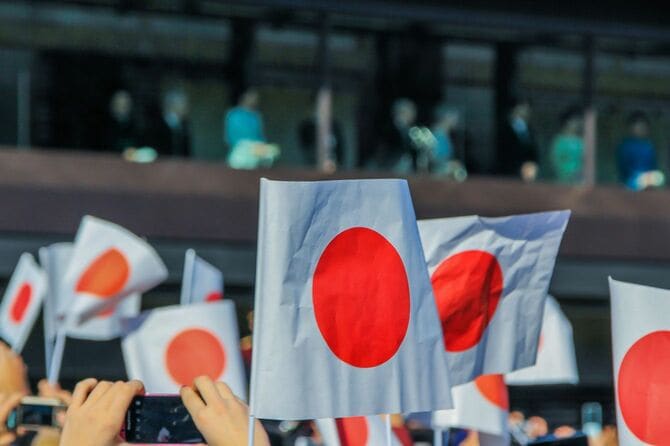神代の舞台として描かれている南九州
“日向”神話とよばれているイワレヒコ(神武)以前の、いわゆる“神代”の三人のミコトたちの舞台として描かれている土地は、今日の宮崎県だけではなく、鹿児島県を含んだ地域であり、物語の展開のうえではむしろ鹿児島県、とくにその西南部の薩摩半島がひんぱんに登場する。これら南九州の土地は、いうまでもなく隼人とよばれた集団の活躍するところでもあった。
このように神話の展開のうえでは、南九州と天皇家の遠い先祖が不離一体の関係にあったのだが、それが神話のうえにとどまらず、実際になんらかの関係があったのか、それとも『古事記』(以下、『記』)・『日本書紀』(以下、『紀』)の編者たちの完全な創作であったのかについては、考古学や民俗学の資料、さらに南九州という土地柄や奈良時代以後の歴史の推移などをも十分に考慮してから、考えをまとめねばならない。それは容易なことではなかろう。
本書の第8章でも少し述べたように、“完全な創作”とみるには無視できない考古学資料がある。といって、もちろん『記・紀』の物語の展開通りの史実があったということは、とうてい考えられない。そこでもう一度、南九州のいわゆる隼人の地域について、微細な資料に目を向けてみよう。
「鵜戸の岩屋が国王の宮殿である」
17世紀のはじめに日本で活躍したイエズス会の通事ジョアン・ロドリーゲスは、『日本教会史』のなかで、“日本人が住んだ最初の地方は九州の日向である。そこに最初の国王神武まで(もちろん東方への移住まで)が住んでいた。日向には鵜戸の岩屋という洞窟があって、そこが国王の宮殿である”という意味の文章を載せている(『大航海時代叢書9 日本教会史 上』岩波書店、1967年)。
ロドリーゲスは、日本人の間で通事伴天連とよばれた。つまり日本語に通暁していたのである。ということは直接、日本人からものを聞くことができた人であるから、彼が残した文章には貴重な情報があると私は考えている。
見通しにすぎないけれども、南九州に天皇家の遠い先祖が根拠地をかまえていたことについてのロドリーゲスの知識は、『記・紀』を読むことから得ただけではなく、九州の人びとから得た伝説をまじえた話であったであろう。