位置エネルギーを運動エネルギーへ変換する
『場所原論』のサブタイトルは、「建築はいかにして場所と接続するか」。この背後には、20世紀の普遍主義が場所と人間を切り離して考えていたという認識がある。分かりやすい例でいえば、ル・コルビュジエの機能主義。コルビュジェの設計した住宅にはピロティがあることが多い。住宅部分は柱の上に浮いたような格好になっている。つまり、地面という物理的な場所から独立している。これは文脈から独立して、機能というか普遍的な価値の象徴作用として理解できる。著者が言う「場所との接続」は、20世紀のコルビュジェとは真逆の方向を示している。
『場所原論』では著者自らが設計した建築物が数多く紹介されている。たとえば亀老山の展望台。この建物は物理的に山と接続しており(言葉で説明するのが難しいのだが、建築物が山に入り込み、山と一体になることによって、「場所を受け入れて」いる)、まさに場所主義の概念を具体化したものとなっている。
宮城県登米町の伝統芸能伝承館。この建物には能舞台がある。しかし能舞台は屋内ではなく、屋外に設置されており、周囲にある森と接合されている。建物と場所をつなぐだけでなく、高額のヒノキ材で作った能舞台をコンクリート覆うという従来の工法を使わずに、低予算で仕上げるという目的もあった。舞台には地元資源であるヒバを使い、屋根は登米玄昌石で葺いてある。いずれも「小さなエレメント」だ。
ひとつひとつ挙げていくとキリがないのだが、もうひとつだけ紹介したい。栃木県の那須にある「石の美術館」。大正期に建てられた米蔵を小さな美術館として再生させるという仕事だ。ここでは地元の石切り場で取れる石を組み立てていく方式が採用された。この手の建築物の建設では、ゼネコンが複数の業者を調整してそれぞれの分担をこなしていく「アセンブリー」の手法をとるのが通常のパターンだ。しかし、この美術館の建設では、そうした縦割りのやり方ではなく、地元の職人だけの力ですべてを仕上げるという方法がとられた。「小さな場所」の概念が具体のレベルで結実した例だ。
このように、著者の手による一連の建築物は、すべて「負ける建築」「場所主義」という概念から発想され、その概念に忠実に具体化されている。きわめて抽象な概念から始まって、ここまで具体的なかたちを持つところまで降りてくる。現実世界から生まれた問題意識が抽象化を経て概念構想の高みまで到達する。すると、抽象概念が位置エネルギーをもつ。それが再び具体へと戻っていくときに、概念の持つ位置エネルギーが運動エネルギーに変換され、現実世界の建築として具体化する。これは僕がイメージする「創造」のど真ん中だ。隈さんの1つひとつの仕事をみると、具体から抽象へ、抽象から具体へという変換過程が手に取るようにわかる。「創造とは何か」がはっきりとした輪郭を持って見えてくる。
戦略をつくるという仕事にも、このようなエネルギー保存の法則が働いている。個別具体的な打ち手に資源を投入しないことにはビジネスにならない。しかし、有効な打ち手を繰り出すためには、まず抽象化して事業のコンセプトを構想する必要がある。優れたコンセプトであれば、そこから次々に具体的な打ち手が触発される。コンセプトのもつ位置エネルギーが運動エネルギーに転換されることで、結果的に動きの強い戦略が生まれる。
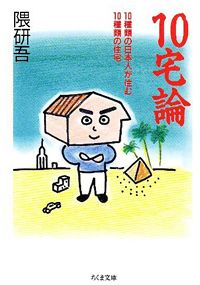
[著]隈 研吾(筑摩書房)
この連載の第14回と15回でとりあげたホットペッパーの戦略はその好例だ(>>記事はこちら)。当初は市場や消費者の行動についての具体的な観察、それに対応した断片的なアクションの試行錯誤が行われる。そうした具体的な断片がもつ運動エネルギーが徐々に抽象化され、「生活圏」「狭域情報」という強力な位置エネルギーをもったコンセプトとして結晶する。ひとたびコンセプトが確立すると、それを具象のレベルに降ろすことによって、さまざまなアクションが次から次へと出てくる。すべてがコンセプトから導出されているので、アクションの間のつながりも自然と太く強くなる。
すでにみたように、抽象と具体の往復運動が絶対的に必要となり、その過程がまる見えになるのが建築の世界だ。建築に関する本や建築家によって書かれた本は、ビジネスの戦略にとって有用な示唆がふんだんに含まれている。その濃度が最も高いのが隈研吾さんによる一連の著作だというのが僕の見解だ。
ということで、前置きが長くなってしまったが、次回は隈さんの多くの著作の中でもひときわユニークな本である『10宅論』の中身について話をする。






