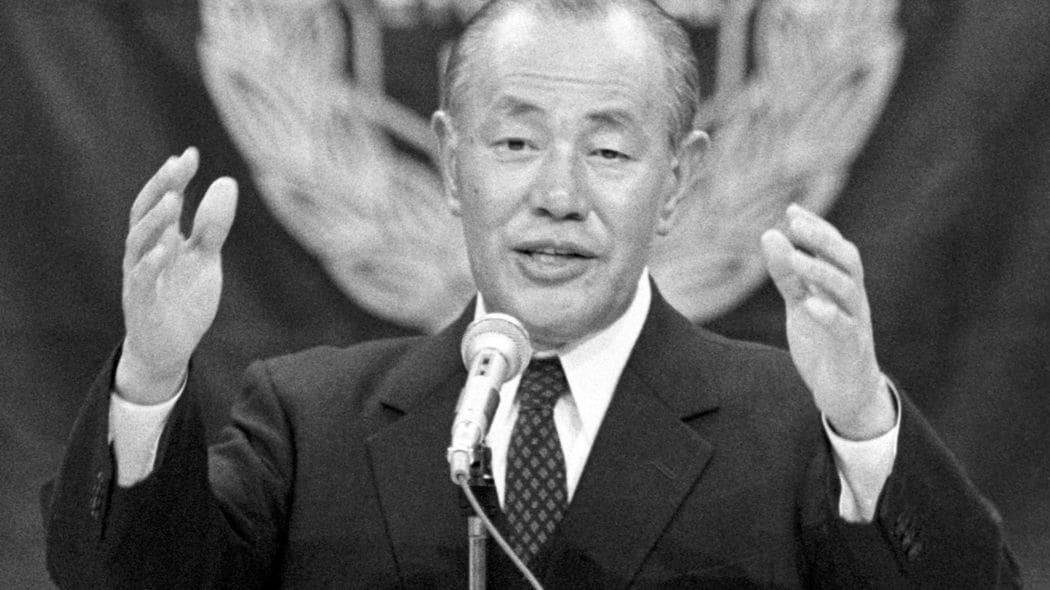※本稿は、草野仁『「伝える」極意』(SBクリエイティブ)の一部を再編集したものです。
「伝わらない」のは“使い方”が原因
①漢語の多い文章
②「言葉をひらいた」文章
いろいろと準備を調え、下調べも万全。何度も練習をしたけれど、自分が期待するほどには、相手に話が伝わっていない気がする。しかし、何がよくないのかがわからない……。こんな思いをしたことはないでしょうか。もしそうなら、ご自分が使っている「言葉」について振り返ってみましょう。ひょっとすると、使い方に原因があるのかもしれません。
私たち放送に関わる人間は、相手が聞いた瞬間に理解できる言葉、平易でわかりやすい言葉を使うことを徹底して心がけています。これを私は「言葉をひらく」と呼んでいます。
言葉に関する仕事をしていると、自然と語彙は豊富になります。
ですがそのぶん、聞いた相手が「えっ、それは何?」と迷ってしまう言葉をとっさに使ってしまうこともありうるのです。そうなると相手は「あの言葉は一体何だったのだろう」と立ち止まって、そこから先の話が頭に入ってこなくなります。
そうならないためにも、私は徹底して「言葉をひらく」ようにしています。とくに気をつけている言葉の代表例は「漢語」です。漢字二文字の言葉は、文字を目で追うときにはすらすらと理解できますが、耳で聞くだけのときは、判断に迷いやすい言葉なのです。実際に、話し言葉の中に二字熟語をたくさん使ってみましょう。
「聞き取りやすく、わかりやすい言葉」がいい
どうでしょう。聞いたときに「“しょうさ”かな、“ちょうさ”かな」「“いぎ”とは、意義? それとも異議?」など、迷う部分がたくさん出てきますね。また、言い回しも全体的に堅い印象です。それよりも、
と言い換えてみたほうが、聞きとりやすく、わかりやすくなりますね。
同じように、
「討論する」は「話し合う」。
「精査する」は「よく調べる」。
「発言する」は「言う」または「おっしゃる」。
このように、できるだけ「ひらいた言葉」に変換して伝えるようにしています。
とはいえ、いつも誰にでもわかる言葉を使えるとは限りません。今は、新しい言葉もどんどん登場していますから、日本語訳の追いついていない横文字をそのまま使わざるを得ないこともあります。
そのときは、放送であれば、ボードに言葉を書いて「こういう意味の言葉です」と説明をしてから本題に入るようにします。読み方も、もとの発音になるべく近づけます。時間の制約があるニュース報道でそこまで細やかに説明するのは難しいかもしれませんが、見ている方たちの理解を進める上では、そのくらいの努力をしなければいけないと思っています。
仕事のプレゼンテーションや面接でも、難しい用語を使って自分を恰好よく見せようとせずに、あくまでも相手(聞き手)ファーストの姿勢を心がけることが、最終的には良い結果につながっていくでしょう。