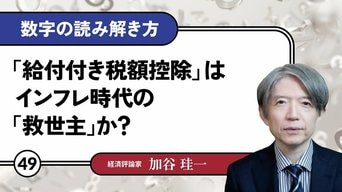三木 卓(みき・たく)
詩人、小説家。1935年生まれ。幼少期を旧満州で過ごし、静岡高校、早大露文科を卒業。詩人としてH氏賞、高見順賞を受け、小説家としては『鶸』で芥川賞、97年『路地』で谷崎潤一郎賞など受賞歴多数。児童文学の分野でも活躍している。2011年、旭日中綬章を受章。
詩人、小説家。1935年生まれ。幼少期を旧満州で過ごし、静岡高校、早大露文科を卒業。詩人としてH氏賞、高見順賞を受け、小説家としては『鶸』で芥川賞、97年『路地』で谷崎潤一郎賞など受賞歴多数。児童文学の分野でも活躍している。2011年、旭日中綬章を受章。
「詩を書いて生きるとはこういうこと。おもしろいけど、少し悲しい」。ある詩人から感想が届いたという。
芥川賞作家であり、詩人や児童文学作家としても知られる三木卓さんが、5年前に亡くなった妻で詩人の桂子さんとのあれこれを小説に書いた。旧満州からの引き揚げ者であり母子家庭で育った夫と、北の港町・八戸の恵まれた商家の出身である妻。失われた暮らしを懐かしむ、情味にあふれた作品に仕上がりそうなものだが、この本は違った。作中の妻「K」は、意外にもとびきりの悪妻なのだ。
「雑誌『群像』に載ったときからかなりの反響がありましてね。ある知人は『いつもニコニコして幸せそうに見えたが、そんなに苦労していたとは知らなかった。愕然としたよ』というハガキをくれました。僕はエッセイを書くときも『陰気な話は書かない』と決めていましたから、驚いた人も多いでしょうね」

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント
(小倉和徳=撮影)