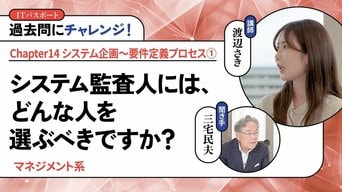※本稿は、柴田昌治『日本的「勤勉」のワナ』(朝日新書)の一部を再編集したものです。
努力が生産性の伸びにほとんど結びついていない
他の競合国がこの数十年の間に急速に生産性を伸ばしている中で、日本も懸命の努力は続けているのですが、その努力がバブル崩壊後の生産性の伸びにはほとんど結びついてはいない、という厳しい現実があります。
生産性とは、投入した資源(労働など)に対する創出した「付加価値」の割合です。より少ない資源からより多くの付加価値が得られるほど、より生産性が高いという関係になります。生産性を高めるのは、豊かな社会を創り上げるためであり、そのためには無駄な「動き」を減らし、価値を生み出す「働き」の部分を増やすことが必要なのです。
しかし、約30年前のバブル崩壊以降、日本の給料はまったく上がらず、世界の水準から取り残されてきている、という事実があります。今、そのことがようやく問題だと認識され始めています。
努力は必死に続けているにもかかわらず、給料の水準は伸びていない。この厳しい現実は、努力の方向性が間違っていることを示しています。
社会全体として新しい価値を生み出せていない
その前提にあるのは、高度経済成長期以来、日本の得意だった経済モデルが通用しなくなってしまったことです。すなわち、日本の代わりを圧倒的に安い人件費でやってしまう国々が、一瞬のうちに世界市場を席巻してしまったのです。従来通りの日本的モデルでは、成り立たない時代になったことが明白になっています。
一方、世界では、米国を中心にデジタル化が急速に進んでいきました。日本も相応の努力はしているのですが、結果として一歩も二歩も後れを取っています。
確かに、個別に見れば素晴らしい結果も残してはいるのですが、残念なことに全体として見れば、新しい価値を生み出せていないのが日本の実態なのです。
今、私たちにいちばん必要とされているのが「創造性」です。しかし、それが当たり前になっていないところにこそ、問題があるのです。
なぜ創造性というものが当たり前になっていないのか。それは、みんなの力を合わせてものづくりに励む、という経済の高度成長を支えてきた旧来の考え方ややり方、いうなれば、ある種の文化が今もそのまま残っているところに問題が潜んでいます。