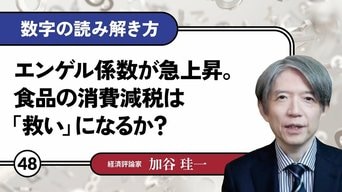現代は情報化社会と呼ばれているが、それは中国古代の戦国時代でも同じだった。
当時は、説客(ぜいかく)と呼ばれる政治ブローカーたちが各国を遊説し、己に有利な情報を触れまわっていた。この真偽がわからない情報の洪水を利用して、いかに成果をあげていくかも、為政者の腕の見せ所だったのだ。
この「情報」という切り口では、次のような話がある。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント