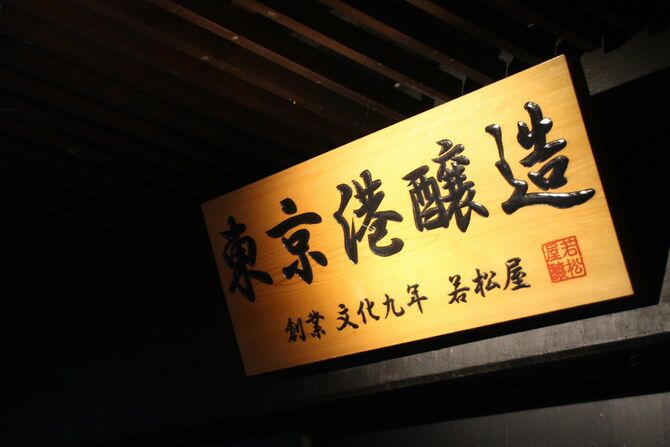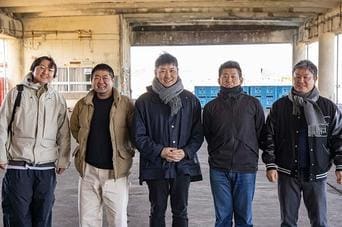東京・港区芝の路地裏に、23区で一軒しかない酒蔵「東京港醸造」がある。鉄筋コンクリートの4階建てビルで造り手は3人、仕込み水は東京の水道水という、伝統的なイメージとは全く異なる酒造りは、効率化・合理化を徹底的に追及した杜氏の手腕によるものだ。酒ジャーナリストの葉石かおりさんが取材した――。
日本三大酒処・伏見で腕を磨いた杜氏
「本当にこんなビルばかりの場所に酒蔵があるの?」
JR田町駅から、日本酒「江戸開城」を醸す東京港醸造に向かって歩きながら、そんな一抹の不安を抱いた。細い路地を入ると、「東京港醸造」ののぼり旗が目に入りようやく安堵。それにしても、ビルに挟まれた4階建ての細長いビルで、しかも東京の水道水を使った酒はどのようにして造られるのだろうか?
これまでの酒造りの概念を覆した代表取締役の寺澤善実さんにお話をうかがった。
寺澤さんは京都の高校を卒業した後、伏見の大手酒造メーカーで20年ほど酒造りをした経験があるベテラン杜氏。寺澤さんが縁もゆかりもなかった東京で初めて仕事をしたのは2000年のこと。会社からの辞令で、「マイクロブリュワリー」の先駆けとも言えるお台場の醸造所で酒造りをすることになったのだ。
7代目から「酒蔵復活」の相談
「お台場の醸造所は52平米という小さなスペースでした。観光地で人も多いのですが、お台場はわざわざ酒を飲みに行く場所ではない。メインは修学旅行生や車で来る家族連れですからね。時代背景を先取りした事業ではあったものの、残念なことに事業の効率化で最後は私一人だけが残りました」
赤字続きで「閉業するかもしれない」という状況下の2006年、「東京港醸造」の共同経営者である齊藤俊一会長から「自社ビルで酒造りをしたい」という相談が寺澤さんに舞い込んだ。
齊藤家は1812年創業の「若松屋」で日本酒を造っていたが、明治末期に廃業した後は雑貨屋を生業としてきた。齊藤さんはその7代目で、約100年ぶりに酒蔵を復活させようとしたのだ。