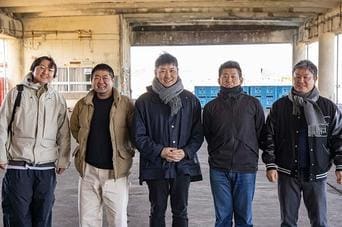お金が貯まる人、貯まらない人の違いはどこにあるのか。消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんは「出費を抑えようと、安くていいものを手に入れようとする。それがお金が貯まらない“落とし穴”になっている」という――。
「いいモノが安く買えた時代」は終わった
物価高が止まらない。節約できない必需品にあたるコメの売価は下がらないままだし、キャベツも白菜も相変わらず高い。おまけに、4月にはビール大手4社が揃ってアルコール飲料を値上げする予定だ。
むろん値上げは食品だけにとどまらず、ティッシュやトイレットペーパーの値上げも予定されている。そうなると家計のために1円でも安いものを探したいのが人情だ。チラシを見比べたり、ネットで情報収集したりと、庶民はそのための努力を惜しまない。今や、安さは価値そのものなのだから。
しかし、安さにも2種類あるのはご存じだろうか。良い安さと悪い安さ、いや、正統な安さと不当な安さと書くほうが正確かもしれない。この違いを見極めておかないと、大事なお金を守れない。長らく日本では、性能がよく、かつ安いモノが手に入ったものだ。しかし、今や「安かろう、悪かろう」の時代にいよいよ突入している。
デフレ時代、激安商品は当たり前
1900年以降のデフレ時代はなかなか給料が上がらず、その懐にあわせて安い店や業態がたくさん生まれた。高く値をつけても売れないし、激安価格で客を引き付けるしかなかったからだ。
私たちになじみ深い100円ショップチェーンが誕生したのもその頃だ。均一ショップの安さの理由はいくつかあるが、人件費や製作コストが安い海外生産の商品を大量に仕入れすることで原価を抑え、100円でも販売することができた。また、利用客の支払いも現金のみにすることで、キャッシュレス決済手数料の負担もなかった。