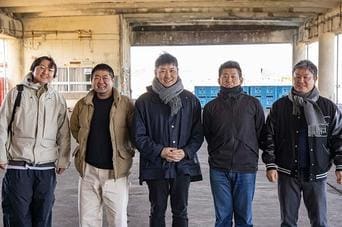※本稿は、佐野雅代『その場で言語化できるメモ』(サンマーク出版)の一部を再編集したものです。
言葉は、「料理」みたいなもの
何かを効果的に伝えようと思うと、つい凝った表現や、自分のオリジナルの言葉を使わなくてはと考えがちになります。
でも、小説家やアーティストのような仕事なら別ですが、多くの仕事においては、むしろシンプルな言葉や表現のほうが好まれるのではないでしょうか。
私は常々、言葉というのは「料理」みたいなものだなと感じます。
たとえば、毎日の食事では、シェフのオリジナル料理のような、もの珍しくて作るのも大変な料理よりも、肉じゃがやカレーなど、手軽でみんなに好まれるおふくろの味のほうがよかったりしますよね。
日々の仕事や生活の中で求められる言葉も、小説のように斬新なセリフやあっと驚く展開よりも、できるだけシンプルな言葉で、お決まりのパターンに沿って表現するほうが伝わりやすいものです。
企画書やプレゼン資料も“レシピ”を頼ろう
なので、企画書やプレゼン資料など仕事上の文章を書く場合も、まったくのゼロからオリジナルの流れや言葉を生み出す必要はありません。
上司や先輩が過去に作ってきた資料を参考にしたり、書式や事例集などをもとにして、ある程度決まったレシピ通りに作ったほうが、結局は伝わりやすい文章になるものです。
私が勤めていた裁判所というのは特に、広く国民みんなが利用するサービスですし、公平さが求められる仕事なので、書式や事例集通りに文章を書くことが重視されていました。また、ビジネスにおいては、お客様との信頼関係を築くために、人間心理に基づいた決まった流れや型に沿って伝えることが大事だといわれています。自分でゼロから考えるより、そうしたテンプレートを使ったほうが、速くて効果もあることでしょう。
このように、定番レシピのようなものを意識したうえで、そこに自分のアイディアを当てはめていくというのが、伝え方の基本的な考え方になります。
そして、料理を作るときには必ず、食べる相手のことを考えて、相手が食べやすい、好みに合った料理を作ろうと思いますよね。その感覚が、「相手目線」に立って伝えるという感覚に近いのではないかと思います。