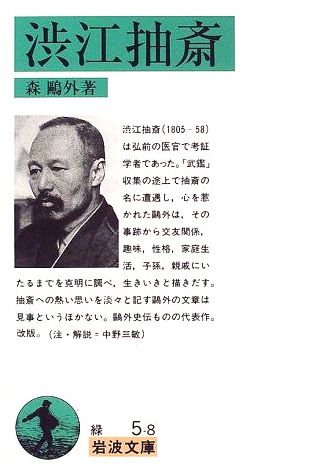鴎外の「伝記2作品」は近代日本文学の最高峰

日本の近代文学で誰が偉い作家かといえば、夏目漱石と谷崎潤一郎、そして森鴎外の3人だと相場はほぼ決まっています。戦前の文壇筋では、谷崎はともかく、漱石や鴎外を褒めるのは素人で、一番偉いのは志賀直哉だと評価が定まっていましたが、ここにきてやっと妥当なところに落ちつきました。
一般的に漱石や谷崎の作品はよく読まれているはずなので、あらためて触れる必要はないでしょう。問題なのは森鴎外です。だいたい、鴎外の小説は美談主義でたいしたことはない。それでも、国語の教科書で『高瀬舟』なんかを無理矢理読まされるものだから、みんなうんざりしてしまう。そもそも教科書にはつまらないものが載るので、教師の教え方も下手に決まっているから、印象が悪くなるのは当たり前。鴎外の作品で本当に価値があるのは、晩年の50代に書いた3つの伝記なのです。
その3作とは、書かれた順に『渋江抽斎』『伊沢蘭軒』『北条霞亭』。いずれも江戸後期の医官でたいへんな読書家だった。鴎外は古本屋で彼らが売った本に出合い、「いったいどんな人がこれほど立派な蔵書を持っていたのだろう」と好奇心を抱いて探り出す。そこから話が始まります。
伝記というと野口英世やリンカーン、エジソンなど誰もが知っている偉人について書かれることが多いけれど、鴎外の方法は違いました。よく知られていない人物を題材にして、探偵小説のように少しずつその人物のことを解き明かし、ときには壁にぶつかって立ち止まるけれど、別の手がかりを見つけてまた前へ突き進んでいく。
この仕組みは、われわれが生活の中で謎に逢着してそれを解いていく様子とおんなしで、これこそ本当の現実だという感じがするのです。しかも、そのプロセスが鴎外一流の見事な文章で書かれている。
先に挙げた3作の中では、僕は『渋江抽斎』と『伊沢蘭軒』がいいと思う。この2作品は近代日本文学の最高峰といえるでしょう。なぜそれほど素晴らしいのか。この2作は続けて書かれたものですが、謎解きの構造がたいへん大仕掛けになっていて、『伊沢蘭軒』の中で、前作で解決されなかった謎がすっかり解けるのです。
それは、渋江抽斎の師にあたる池田京水の家の跡継ぎ問題です。幕府の医官である家長の池田獨美と血のつながっていた京水は、なぜか家を出て独立し、村岡という男が養子になって家を継ぐ。どうして京水は家を出たのか。それを鴎外は京水の子孫から借りた京水自筆の巻物を読んで理解できたと著します。
実は60歳をすぎた獨美には沢という30歳も年下の3人目の後妻がいた。この沢には情夫がいて、情夫に家を継がせたいので京水を廃嫡しろと獨美に訴える。京水は事情を察して自ら退き、結局は間男の弟子である村岡が跡を継ぐことになったというのです。
ここで一つ僕が不満なのは、若い女房の姦通を黙認してしかも言いなりになるに近い60すぎの男という素晴らしい題材を見つけながら、どうしてそれを掘り下げて書こうとしなかったのか。伝記では無理でも、小説ならばおもしろく書けるでしょう。
ただし、書けない理由は推測できます。一つには当時姦通は刑法上の罪になること。鴎外は40代に『ヰタ・セクスアリス』という性的な体験を考察する小説を書いて、発禁処分などのお咎めを受けた。つまり、姦通をテーマにすることにためらいがあったのではないか。鴎外は知っての通り高級官吏で、お上からもらう給料で暮らしを立てて文学を楽しむ身でした。前科者になれば経済的基盤がなくなってしまう。
なお、作家の宇野浩二や石川淳はこれら2作よりも3作目の『北条霞亭』のほうが上だと言っています。石川淳の説によると、鴎外は北条霞亭という男を夢中になって調べる中で、この男が俗物だと悟った。でも、鴎外はこれが人間なのだと考えて書き続けた。そこが素晴らしいと。石川淳が『北条霞亭』から感じとったのは、霞亭の俗物性に接することによって鴎外が自分の俗物性に気づいてしまい、その困り方が作品に表れていて文学的に価値があるということでしょう。