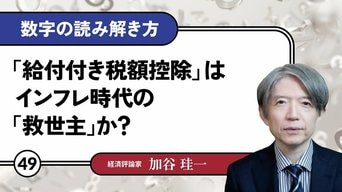約2000年前の中国。中原を駆けた男たちは、それぞれの夢を追い、やがて死んでいった――。彼らのドラマはなぜ私たちを魅了し続けるのか。北方謙三氏は『三国志』(全13巻)で、前例のない人物描写に挑み、高い評価を得た。氏は英傑の生き様からなにを読みとったのか。
「乱世の奸雄」は『正史三国志』において陳寿が許子将(きょししょう)という人物の言葉を借りて曹操孟徳(もうとく)を評した言葉だ。本当は「治世の能臣(ちせいののうしん)」という対になる言葉があるが、「乱世の奸雄」ばかりが独り歩きして、悪役のイメージを決定付けた。

曹操●155年生まれ。字は孟徳。後漢に仕え黄巾の乱には騎都尉として参戦。董卓の死後は袁紹を破って河北・中原の覇権を握った。江南の平定を目指したが、赤壁の戦いで劉備・孫権の連合軍に敗れ、天下統一は果たせなかった。享年66。
しかし単に奸智に長けていただけで、群雄割拠の三国時代に最大の版図を築けようか。私は曹操こそ、三国志の世界で最も苛烈、果敢に戦い、戦い続けることに最も純粋な戦人だったと思う。赤壁(せきへき)で周瑜(しゅうゆ)を撃破していればあるいは覇道は成ったかもしれない。その意味で悲劇の英雄でもある。
曹操が生涯に直接戦った戦闘は計67。すさまじい数だ。しかも、そのうちの約50は負け戦である。なぜ折れることなく、かくも激しく戦えたのか。それは「なぜ曹操は曹操たりえたか」という問いに等しい。自らの手で漢土(かんど)14州を統一したかったのは確かだろうが、その根源にあったのは自らの国家観に対する信念の強さだったに違いない。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント