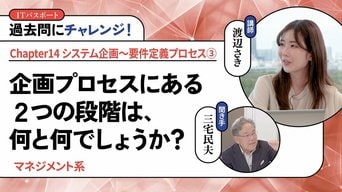※本稿は、西田亮介『エモさと報道』(ゲンロン)の一部を再編集したものです。
信頼性の高いメディア群「トラストな情報基盤」
「トラストな情報基盤」とは、正確な情報を収集し、信頼できるコンテンツの制作と流通を具体的に保障する制度、仕組み、機能を有する報道事業者等の総体のことである。
言葉を足すなら、人材育成、拠点(支局)形成、自己批判、訂正、透明性や説明責任など社会と対話する意欲を外形的に確認できるメディアによって構成される、ソフトとハード、そして有形無形の基盤のことである。
つまりそれは「誤報を起こさないメディア」「間違わないメディア」のことではない。間違えたら訂正を行う、信頼できる蓋然性の高いメディア群と考えてほしい。
人を育て、支局など取材拠点を維持し、記者を配置し、デスクなど精査のための体制を構築するには、莫大な初期投資とランニングコストが必要となる。情報を報道事業者が独占し、そのことが利益に繫がった時代が終わり、こうした体制の構築が直接売上や利益には繫がらなくなったにもかかわらず、である。
新興のコンテンツ事業者はそれらに対するコストを限りなくゼロに近づけているか、ほとんど必要としない。しかしアテンションを巡る競争において、動画をはじめとするネット全般の事業領域で、報道事業者とコンテンツ事業者は競合関係にあるといってよいだろう。
民業としての報道機関の歴史は意外と浅い
報道事業者は極めて厳しい競争条件に立たされるとともに、そもそも日本語圏という「小さな」市場で、将来において民業として報道機関が成立するのかということすら問われる時代になってしまった。ここでは深入りしないが、民業としての報道機関が成立した期間は歴史上短く、日本では新聞で150年、戦後から数えれば80年、テレビにいたっては1950年代から60年超程度の期間に過ぎないのである。
むしろそのような時代のほうが僥倖だったのかもしれないとさえ思えてこないだろうか。
インターネット、SNS、動画という新しい事業形態が全面化した環境のもとで、なぜ「民業としての報道」の成立、存続を自明視できるのだろうか。放送、新聞業界がここから盛り返すことは並大抵ではないはずだ。