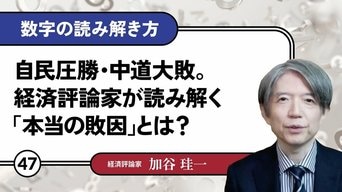「自分の名刺になる本を書こうと思いました」

松本麗華(まつもと・りか)
1983年生まれ。オウム真理教の教祖・麻原彰晃と松本知子の三女として生まれる。95年に父が逮捕された後は、唯一の「正大師」としてさまざまな問題に巻き込まれていく。その後、教団から離れ、文教大学に入学、心理学を学ぶ。現在も、心理カウンセラーの勉強を続けている。
1983年生まれ。オウム真理教の教祖・麻原彰晃と松本知子の三女として生まれる。95年に父が逮捕された後は、唯一の「正大師」としてさまざまな問題に巻き込まれていく。その後、教団から離れ、文教大学に入学、心理学を学ぶ。現在も、心理カウンセラーの勉強を続けている。
カバーは顔写真。内容は自分史。彼女が話すように、自身の半生を綴った本はしばしば名刺にたとえられる。しかし本書に紙片一枚のような軽さはない。それは著者がかつてアーチャリーと呼ばれた、麻原彰晃の三女・松本麗華であるからだ。
地下鉄サリン事件当時は11歳。オウム真理教での階級は上から2番目の正大師だった。事件後は教団から離れ、アルバイトをしながら、大学で心理学を学んだ。事件から20年。なぜ本を書いたのか。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント
(永井 浩=撮影)