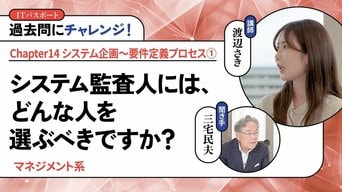患者が医師と適切なコミュニケーションをするにはどうすればいいか。認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長の山口育子さんは「医療分野では、医療者と患者に情報の“非対称”があるため、同じ日本語でコミュニケーションしているのにイメージの隔たりがある」という。鳥取大学医学部附属病院の武中篤病院長との対談をお届けする――。
※本稿は、鳥取大学医学部附属病院広報誌『カニジル 21杯目』の一部を再編集したものです。
20代半ばで卵巣がん、3年生きる確率は2割
【武中篤(鳥取大学医学部附属病院長)】山口さんと初めてお会いしたのは、昨年8月に、秋田県で行われた医学教育学会でした。大会長が、私の友人、泌尿器科の教授。彼らとの食事会に山口さんがいらっしゃった。ご挨拶すると、来月、講演で鳥取大学に行くんですと(笑い)。不思議な縁を感じました。
【山口育子(ささえあい医療人権センターCOML 理事長)】私も初めてお会いしたという感じがしなかったです(笑い)。
【武中】山口さんが医療と関わることになったのは、ご自身が患者となったときからですよね。
【山口】1990年、あと2カ月で25歳というときに卵巣がんと診断されました。当時の主治医は両親に「3年生きる確率は、2割ありません。20代半ばで卵巣がん、しかも残りわずかな人生と知れば、必ず精神状態はぼろぼろになります。本当のことは言わないでください」と箝口令を敷いていました。
【武中】その頃、私は医師になっていましたが、振り返ると“がん告知”は一般的ではありませんでした。
【山口】手術予定を待たずに破裂しての緊急手術、その後の抗がん剤治療は「癒着止め」という名目で行われました。私は1歳1カ月と2歳9カ月のときに弟が生まれています。1歳のときから弟のおむつを持って来たりしていたそうです(笑い)。
幼いときから自分のことは自分で決める、他人の決めたことに従うのは大嫌いという性格。自分に起きている真実を知ることができないなんてあり得ない。そしていろいろと交渉して自分の病名を知りました。