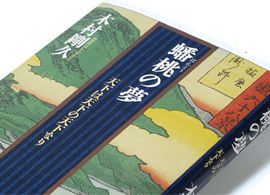江戸時代、三井家の3代目・高房は『町人考見録』を著し、「大名にカネを貸すべからず」という家訓を残したそうだ。そこには踏み倒し大名ワーストテンが記されており、仙台伊達家はその代表格だったという。
13歳で大阪の中堅米仲買、升屋の丁稚となり、25歳で大番頭となった山片蟠桃(ばんとう)は、それまで仙台藩に資金を提供していた蔵元が「用立てる資金のほうが、任される蔵米の額を超過する」と投げ出した後、代わって藩を支えた商人である。財政に窮していた仙台藩に融資を続け、藩の財政破綻によって升屋も連鎖倒産する危機を、類まれな商才で切り抜けた。バブルの田沼意次に代わり、松平定信による徹底した緊縮財政の「寛政の改革」が実施された時代のことである。
水の都である大阪は、全国から米が集まり、ここで米価が決定され、米市場の中心地として発展した。大阪が「天下の台所」と呼ばれた所以である。各藩の財務担当者は蔵屋敷が並ぶ大阪に出先機関を置き、藩米を担保として、蔵元や米仲買を通じて資金の調達をしていた。このため米を扱う商人は、銀行の役割も担っていたのである。仙台藩に巨額の資金を貸し付けていた蟠桃は、米の相場だけでなく、政治が絡む金融の仕組みについても頭に叩き込んだ。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント