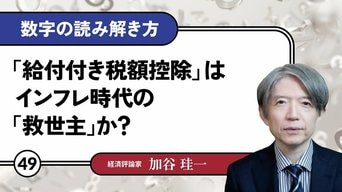3年前の夏、元文部大臣の赤松良子氏や元宮城県知事の浅野史郎氏らとともに「村木厚子さんを支援する会」の呼びかけ人をつとめた。無条件に村木さんの無実を信じていたからだ。家族や友人を含めて考えてみても、村木さんこそが、軽犯罪や交通違反を含めたあらゆる犯罪からもっとも遠い存在なのだ。村木厚子さんを評して聖母のような存在だという人が少なくない。
その村木さんを逮捕し、半年近く拘留した検察に対して抱いた感想は、怒りや恐怖ではなく、呆れと失望であった。少なくとも当時の大阪地検特捜部には人を見る目がまったくないということであり、この程度の能力では、逆に本物の贈収賄犯や市場経済犯を見落とすこともあるだろうと思った。むしろ日本の秩序や市場はこれまでどおり守られるのであろうかと心配になったのだ。
本書はその素人の勘があながちハズレではないことを、さまざまな観点から解説してくれるおススメ本だ。著者は司法ジャーナリズムの第一人者。永田町と霞が関の権力構造を追いつづけた記者だ。ただただ検察の失敗を糾弾するという立場ではない。検察は国民の共有資産であり、重要な統治装置だという立場から、建設的な提言まで行っている。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント