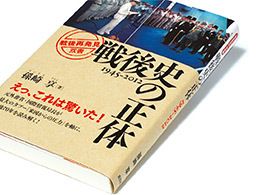20万部超という異例の売れ行きを見せている本書。
「アングロサクソンが植民地から出ていくときは、必ず領土問題を残しておく」という指摘や、60年安保闘争の背景の記述は興味深い。陰謀論の一言で片付けるのは、手放しの肯定と同様に安易であろう。
「たとえ正論でも、群れから離れて論陣を張れば干される。大きく間違っても群れのなかで論を述べていれば、つねに主流を歩める。そして群れのなかにいさえすれば、いくら間違った発言をしても、あとで検証されることはない」(340ページ)ような日本の言論界で、これまでタブー視されてきた米国の圧力・意向という視点から戦後史を見直した著者をリスペクトしたい。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント