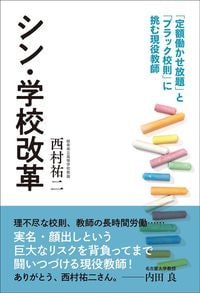令和時代に即した校則はどうあるべきなのか
制服以外の選択肢が認められるようになった結果、勤務校では身だしなみ指導もなくなりました。
しかし制服の着用義務や身だしなみ指導をなくしたからといって、生徒が荒れるとか地域からクレームが入るとか、心配されていたような懸念は何ひとつ起きません。
また生徒からは、「実はコロナ前は制服が苦手で学校に行くのが辛かったんです」と打ち明けられることもありました。制服の着用が当たり前だったときには、そんな本音を口に出すことすら憚られていたと言います。
2023年5月8日、新型コロナウィルスの感染法上の位置付けが「5類」となり、学校現場ではにわかに「アフターコロナ」に向けた急激な揺り戻しが始まっています。
2021年11月に行われた名古屋大学研究チームの全国調査によると、「コロナ禍で削減された業務は、コロナ禍が収束すると元に戻る」と答えた中学校教員は65.7%に達しました(N=458)。
私の勤務校でも、コロナ後の校則や学校行事をどうするのかといった議論が、毎日のように行われています。
昭和時代から変わっていないような学校文化が多い中で、多様性を旨とした令和時代に即した校則はどうあるべきなのか。
コロナ禍での経験も踏まえつつ、まさに今、教師自身が考えなくてはなりません。