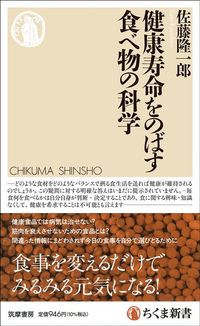高齢になってからのカロリー制限は無意味
ただし高齢になってカロリー制限をすることに意味はありません。この機構を説明する分子として、サーチュインという長寿遺伝子に注目が集まっています。
サーチュイン活性化にはNAD(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)が必要ですがNADの吸収率は低く、その前駆物質であるNMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)の投与によりサーチュインが活性化されることが確認されています。
現時点ではNMNは大変高価ですが、調製法の改良により安価で供給されるようになれば、カロリー制限することなく老化速度を抑えることが可能になるでしょう。健康寿命延伸に結びつく食品成分・化合物の研究・開発は日々発展を遂げています。特に後期高齢者(75歳以上)においては、食が細り通常の食生活では健康維持が難しくなることから、これらのサプリメントを活用してでも、自立活動が可能な時期を1日でも延ばすことが大事です。
(6)ウォーキングは2000歩ごとに死亡リスクを下げます。数千歩を時速3.5km程度で歩く習慣をつけましょう。「歩こう♪ 歩こう♪ 私は元気♪」と心の中で歌いつつ。
本稿では食生活と並行して大事な運動習慣についてはほとんど語ってきませんでした。最後に、ウォーキングの歩数と健康に関する2022年の興味深い論文を紹介したいと思います。
1万歩までは歩けば歩くほど健康になる
イギリスにおいて40歳から79歳の成人約8万人の1日の歩行数と死亡リスクの関係を解析しています。7年間の追跡調査の過程で1325人が癌で、664人が心臓血管疾患で死亡しています。この調査の結果、1日1万歩までは歩数が多いほど、癌死亡、心臓血管疾患死亡、全死亡のリスクが低いことがわかりました(*2)。
また、2000歩多いごとに、癌死亡リスクは11%、心臓血管疾患死亡リスクは10%、全死亡リスクは8%低下するという結果で、少ない歩数でもそれなりの効果が認められました。一方、1万歩を超えて歩いても効果はほとんど上がりませんでした。
さらにどの死亡リスクも、毎分80歩程度の歩行速度がもっとも効果的な速度でした。1歩を70cmとすると時速3.4km、80cmとすると時速3.8kmに相当します。これら数字から計算すると、可能であれば1万歩を目標に、2時間程度で歩く習慣が理想です。この習慣を毎日行うのが厳しい時には、2000歩ごとに効果が認められることを心の支えに、少ない歩数でもウォーキングを続けることは健康維持、健康寿命の延伸に繫がることが期待されます。
(*2)https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2796058