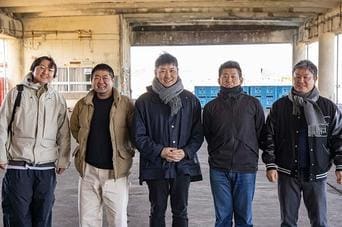「別れ」はただの喪失体験ではない
わたしたちは何かを掴んだら執着が生まれ、「得たものを離さない、失いたくない」という方向へと心が向かいやすいものです。ただ、何かの拍子にパッと手離してみると、余白が生まれたからこそまったく別の新しい何かがやってくることがあります。
手離してみない限り、何が入ってくるのかは誰にも分かりません。別れにも同じような側面があるのだと思います。別れには、喪失感が襲います。しかし、「失うと同時に、何かを得ているのだ」と考えれば、別れというものはただの喪失体験にとどまるものではなく、何か別のものを受け取っている体験でもあるのだと思います。
今の混迷した時代も、まさにそういう転機であると言えます。いろいろな社会基盤自体が大きく揺らぎ、世の中が大きな変化を迎えています。わたしたちがこれまで掴んで離さなかったものが手から離れていっている時代ですが、同時にまったく新しい何かがわたしたちの中へと入ってくる時代でもあるのではないでしょうか。失ったものにだけ注目するのではなく、得たものを探してみることも大事ではないかと思うのです。
わたしは医療現場に立ち、亡くなる方を看取ることもあります。わたしたちは何かを考え悩んでいるときにも、生きている側の視点だけでものごとを考えがちです。しかし、この社会や自然、そして備わっている「いのち」も、すべては過去に亡くなった方々から贈られ、受け取ったものです。「さようなら」も、過去を生きた人々があらゆる言葉を使う中で生き残り、今こうして使っています。言葉もすべて死者からの贈り物なのです。
コロナ禍こそ新しく入ってきたものに目を向けるべき
「今ここに生きている」ということがいかに貴重なことであるかは、死者の視点から「いのち」を考えない限り答えは出てきません。「いのち」を考えるときに、死者を想うことは大切なことです。そのことで、生の尊厳や価値が立ち上がって来るのだと思います。膨大な死者たちからの贈り物によって「生の世界」が存在していることを想像できたときに、「いのち」が受け渡されてきた重みを実感できるのだろうと思います。
過去の「いのち」を受けとり、未来へと生きる。絶え間なく連続している時の流れの中で、わたしたちは今という永遠なる瞬間を生き続けています。「さようなら」という言葉を使うことで、過去・現在・未来をつなげるようにして「今」を生きているのです。
「さようなら」は、他者への別れの言葉であると同時に、自分自身への別れの言葉でもあります。「過去の自分」をありのまま受け止めたうえで、過去・現在・未来の流れを生きていく。無常で変化し続ける自分に対しての、別れの言葉でもあるのでしょう。
コロナ禍の時代でも、手に掴んで離さなかったものが、いつのまにか手から零れ落ちて「さよなら」していることがあります。そのことで、まったく新しい何かが手の中に入り込んできているとしたら、そうしたものを発見していく時期です。そうした発見こそが、新しい時代の光明となるのだろうと思います。