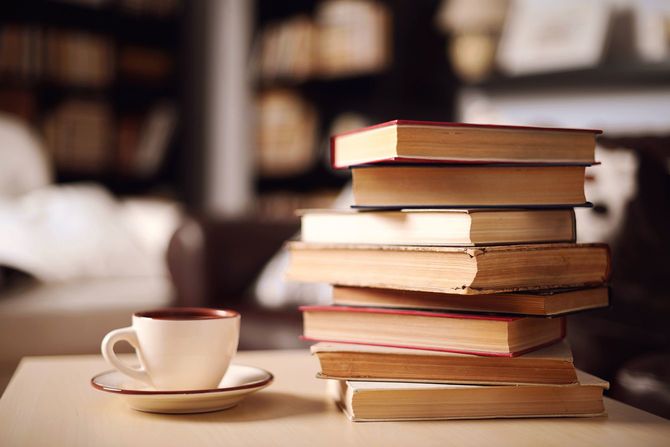自分の言葉として使いこなしてこそ「教養」
このように見てくると、シェイクスピアにしてもマックス・ウェーバーにしても、自らの思考や判断において使いこなせる実践技法にまで習得していなくてはならない。まさに言語能力として肉体化されていないと意味がないのだ。
その意味では、自己言語化レベルまで読み込むなら、コミックの『キングダム』や『鬼滅の刃』でも構わない。大事なことは「アーツ」、技法として身体化できているか否かであり、ディテールの知識ではない。
かの福沢諭吉が『学問のすゝめ』で日本人が学ぶべしとしている「教養科目」も、簿記会計、数学、英語など、まさにいろいろな領域で使われる言語的な科目ばかりである。
最初に言葉ありき。人間は言語でものを考える。プログラミング言語もまさに言語であり、コンピュータを動かす言語体系を一つでもいいから習得しておくことは、これからの時代の言語能力≒考える能力を高めることにつながる。
ちなみに経営者を目指すなら簿記会計を習得しておくことは必須である。会計業務がAI化、自動化されても、簿記会計の基本構造を言語レベルで叩き込んでおかないと、出てきた会計数値、決算数字をもとに経営について考えることができないからだ。もっとプリミティヴには、粉飾決算やプログラミングのバグによる間違った決算に気づくことも不可能である。
「うんちく教養」は無用の長物
このように知識を単なるうんちくに留めず、自分の思考や行動に応用できるようになるレベルまで自己言語化するには、相当の訓練が必要だ。オックスブリッジに代表される欧米のリベラルアーツ教育において少人数教育が行われ、正解のない問いを立て、それについて徹底的な議論が繰り返されるのは、そのためだ。だから本来の教養とは学ぶものというより、鍛錬に鍛錬を重ねて習得するものというほうが実態に合っている。
それに対して、現在の日本の大学におけるリベラルアーツ教育は、単なる知識の詰め込みになってしまっている。残念ながら東大の教養課程も概ねにおいて例外ではない。
これは高度成長時代に、工業化社会に適合した人材をいち早く、大量に世の中に送り込む必要があったからだろう。大学の2年間でさらっと知識を身につけさせ、とっとと社会に送り出すことが重要だったのだ。しかし、そのモデルは実社会ではとっくに耐用期限が終わっている。
その一方で、テレビ番組ではクイズ王、すなわち正解がある問いに素早く答える超優等生としての「東大王」が評判になっている。すなわち東大生≒「うんちく王」として持ち上げられるようになってしまっているのだから、何とも皮肉である。
政治家でも経済人でも、世に「教養人」と呼ばれる人は「うんちく王」とほぼ同じで、教養はあるけれどその教養が邪魔をして実践力、突破力がイマイチ、要はリアルリーダーとしては「??」ということが暗に示唆されている場合が少なくない。だとしたらリーダーにとってそんな「うんちく教養」は無用の長物である。