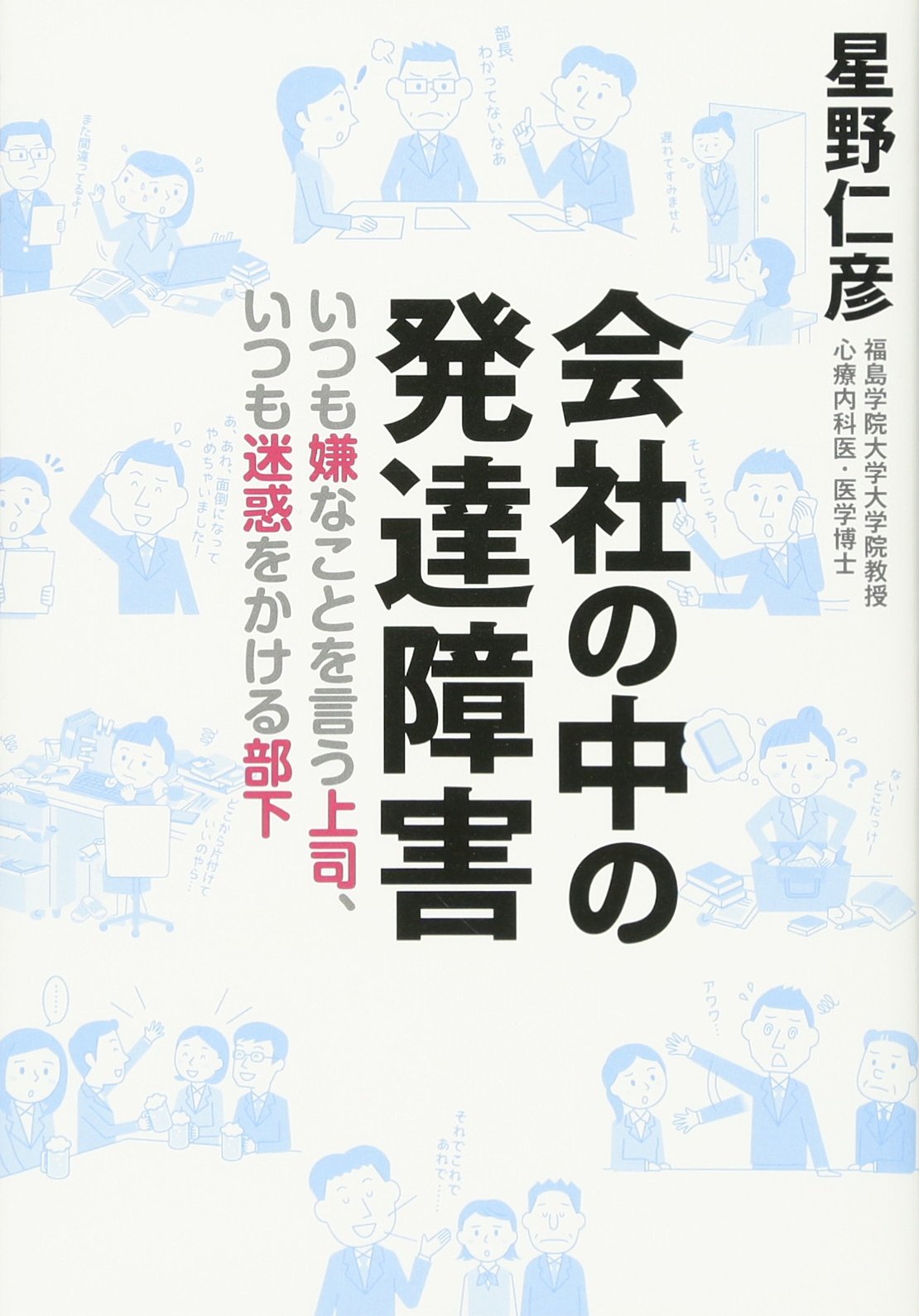※本稿は星野仁彦『会社の中の発達障害 いつも嫌なことを言う上司、いつも迷惑をかける部下』(集英社)の第4章「発達障害に気づいて三十年──ある心療内科医の体験記」を再編集したものです。
「この子、ちょっとおかしいんじゃないの?」
子どもの頃、私は3歳を過ぎてもほとんど言葉を話すことがなく、両親はとても心配したようです。4歳を過ぎる頃には堰(せき) を切ったようにしゃべり始めたそうですが、吃音(きつおん)が青年期になるまで残り、人前で話すのはとても苦痛でした。
幼児期や小学校低学年の記憶はほとんど断片的にしかありません。これも発達障害者の特徴の一つでしょう。
そんな断片的な記憶の一つに、3歳頃の出来事があります。私はいわゆる癇(かん)の強い子どもで、些細なことでかんしゃくを起こし、火がついたように泣き喚(わめ)くことなど日常茶飯事。
ある日、そんな私を見た祖母が「この子、ちょっとおかしいんじゃないの?」と言ったのです。そのとき、3歳児の私は祖母に向かって「お前、早く帰れ!」と、ふてぶてしく言い放ちました。分別もつかぬ子どもの言うこととはいえ、思ったことをなんでも口に出してしまうという性分は幼児期にはすでにあったようです。その後の人生でも、私は場や相手をわきまえず思ったことを口にする失敗を何度も繰り返すことになります。
4歳で幼稚園に入園しましたが、登園初日、知らない人間が大勢いる騒がしい場所に連れてこられた私は大パニックに陥り、手がつけられないほど激しく泣き喚きました。
発達障害の人の多くは、環境の変化に弱く、分離不安や対人不安が強いといわれています。私にもその傾向は顕著にあったようです。常軌を逸した騒ぎ方で、結局、私の幼稚園生活はわずか1日で終わりました。
一生懸命努力しても「だらしない子」
小学生時代、算数と国語は何とか人並みにできましたが、ほかの科目は全滅でした。特に実技系の体育は、鉄棒、跳び箱、ボール競技などまさに手も足も出ず、音楽では、音符はまったく読めず、リズム感もなく、縦笛でドレミさえまともに吹けません。手先が非常に不器用なため、ヒモ結び、折り紙、ハサミを使った作業、布や紙の切り貼り、版画など、図画工作などはことごとくできませんでした。