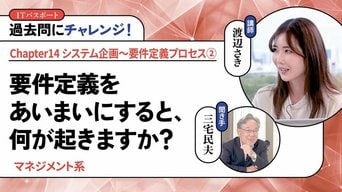藤沢武夫●1910年、東京生まれ。28年旧制京華中学卒。丸二製鋼所、日本機工研究所などを経て、49年本田技研常務取締役就任。52年に同社専務、64年副社長を経て、73~83年取締役最高顧問。
本田宗一郎と藤沢武夫の関係は、リーダーと補佐役の関係として語られることが多いが、あまりしっくりとこない。本田が技術一筋の人であり、一般的な意味での経営は、ほぼ藤沢が引き受けていたことを考えれば、むしろ藤沢こそリーダーと見るのが、「常識的」というものだろう。
しかし、今なお補佐役というイメージを残し続けていることこそ、実は藤沢にとっては勲章なのではないかと思う。なぜなら、彼の経営者人生は「地位に幻惑される人間心理」というべきものとの闘いであり、補佐役という称号は、その闘いに彼が真摯に向き合ったことの証しにほかならないからだ。
たとえば、研究所の独立という事跡がある。まだホンダが大企業でもなかった1960年、藤沢は周囲を粘り強く説き伏せ、本田技術研究所を分離・独立させている。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント
(図版=奈良雅弘 図版デザイン=ライヴ・アート)