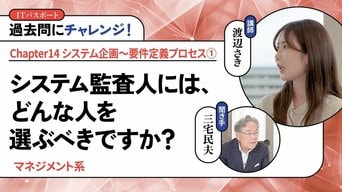暴露後の予防が可能なワクチン
ワクチンというと、多くの人は「感染症にさらされる前に、あらかじめ接種しておくもの」と考えるでしょう。確かに多くのワクチンについては、その通りです。
みなさんになじみが深いのは、子どもの定期接種のワクチンのほか、インフルエンザワクチン、新型コロナワクチンなどだと思います。そのほとんどは、病気にかからないよう事前に接種するワクチンです。
しかし、「暴露後予防」といって、すでにウイルスや細菌にさらされたあとでも、感染成立や発症を防ぐためにワクチンを接種することがあります。
感染症のなかには、ウイルスや細菌が体に入り込んでから、実際に感染が成立して発症に至るまでに時間がかかるものも存在します。そうした病気では曝露直後のタイミングでワクチンを接種すれば、発症を阻止できることもあるのです。ひとたび発症すると命を落とす可能性が極めて高い感染症については、曝露後予防の知識を持っているかどうかで、生死が分かれることすらあるといえます。
意外と身近な「狂犬病」の恐ろしさ
そうした病気の代表例が、狂犬病です。狂犬病はいったん発症すると、致死率がほぼ100%に達する非常に恐ろしい感染症です。
狂犬病ウイルスが神経を伝って脳に到達すると、発熱や頭痛に続き、幻覚、錯乱、興奮状態といった神経症状が現れます。
特に特徴的なのが、水を見たり飲もうとしたりするだけで強い喉のけいれんを起こす「恐水症」です。これは飲み込もうとする動きが苦痛を伴うためで、患者は極度の喉の渇きに苦しむにもかかわらず、水を避けるようになります。症状が進行すると昏睡状態に陥り、最終的には心肺停止に至ります。現代医学でも有効な治療法はありません。
日本は狂犬病の清浄国であり、国内における日常生活で感染するリスクは、ゼロではありませんが、ほとんどないといえます。これは犬への狂犬病ワクチンの接種が法律で義務づけられていること、動物の輸入検疫を徹底してきた結果です。