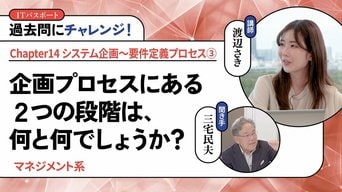奔放な女性作家を体現した宇野千代の生涯はどのようなものだったか。男に尽くした世話女房として知られる宇野だが、クスリに溺れながら男たちの間を渡り歩いた30歳の日々を「青春」として振り返っているという。歴史エッセイストの堀江宏樹さんが書いた『文豪 不適切にもほどがある話』より紹介しよう――。
※本稿は、堀江宏樹『文豪 不適切にもほどがある話』(三笠書房)の一部を再編集したものです。
奔放な「女流作家」のイメージを完全に体現して生きた文豪
川端康成から「もっともすぐれた叙情作家」と評価された宇野千代。大正・昭和・平成にかけ、世間が想像する奔放な「女流作家」のイメージを完全に体現して生きた文豪でした。
宇野はその長い生涯でいくつか自伝的作品を書いていますが、とくに傑作なのが『私の文学的回想記』です。
大正10(1921)年、「時事新報」と「中央公論」が主催した懸賞小説に、宇野は応募し、生まれてはじめて書いた短編小説『脂粉の顔』で一等当選しています。
そして、第二作『墓を暴く』で366円――宇野いわく、「いまで言えば、百五十万円」(消費者物価指数をもとにすれば現在の約250万円)という高額のギャラを、現金手渡しで(!)手に入れてしまった彼女の中で、これまで大事にしてきたものが崩れ落ちる感覚があったようですね。