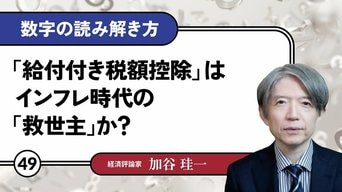「銃後の女性たち」が強いられた戦争とは
戦争体験といえば、戦場の出来事や空襲の記憶・証言に注目が集まります。しかし、戦後80年を経てもなお、埋もれたままになっている"もうひとつの戦争"があります。それは、銃後にいた女性たちが強いられた戦争です。
敗戦直後の旧満州(中国東北部)で起きた性暴力の記録、そして特攻隊員を見送った女性たち……。本稿でご紹介するのは、いずれも長年語られることなく、ようやく近年になって表に出てきた証言の数々です。
本稿ではプレジデントオンラインで配信した3つの記事を紹介します。過酷な選択を強いられた満州に渡った女性たち、婚約者の墓を守り続けた女性の言葉からは、時代に飲み込まれた「個人」の姿が、静かに、しかし力強く浮かび上がってきます。
662人を日本に帰すため、ソ連兵の性的暴行に耐えた未婚女性15人の苦し
※出典:プレジデントオンライン(2020年8月9日公開)
敗戦直後の旧満州では、関東軍が撤退し、日本から渡った開拓団の人たちが孤立。暴徒化した現地人やソ連兵の襲撃に晒されました。岐阜県白川町(旧黒川村)の人たちからなる黒川開拓団もその一つで、記事では団員の命を守るため、ソ連兵と取引をすることになった経緯が紹介されています。<記事を読む>
ソ連兵が付けた条件は、若い女性をソ連兵に差し出すことでした。選ばれたのは18歳から21歳までの未婚女性15人で、ベニヤ板張りの"接待場"で泣きながら暴行に耐えたそうです。筆者の五木寛之さんは「662人の開拓団のうち451人が生きて帰れたのは、まさに彼女たちの犠牲のおかげだったと言っていいでしょう」と述べています。
しかし、帰国後に彼女たちを待っていたのは、中傷と差別の視線でした。「汚れた女」「露助のおもちゃ」という言葉が彼女たちを深く傷つけ、声を上げることすら許されませんでした。
それでも、ある女性が「真実を封印したままでは死ねない」と立ち上がり、「乙女の碑」が建てられました。碑文には体験の詳細が記されましたが、15人の名前は今も刻まれていません。未来に語り継ぐべき「戦争の記憶」とは何かを考えさせられます。
ソ連兵への「いけにえ」にされた女性は蔑視された…満蒙開拓団の少女が証言する「性接待」のやるせない記憶
※出典:プレジデントオンライン(2023年8月1日公開)
記事では、長野県出身の北村栄美さんが紹介されています。満蒙開拓団で敗戦を迎えた少女で、彼女が語る記憶は「語られざる戦争」の断片を今に伝えています。ソ連兵が「女を出せ」と民家に押し入り、顔を黒く塗って男装しても見破られる――そんな恐怖の日々の中、開拓団では「他団の2人の女性がいけにえになってくれた」と語られています。<記事を読む>
記事では、ソ連兵が見えると屋根に上り旗で合図を送り、女性たちを守ろうとした子供のエピソードが挙げられています。彼らは「生きるために平等」であり、学校もなく、学力差も関係なく、できることを分担し合いました。そのさまを北村さんは、「今から思うと、すがすがしい」と振り返ります。
見逃せないのが、ソ連兵の「いけにえ」となっていた2人の女性。なんとか帰還した2人ですが、「どやったね? 大きかったね?」などの心ない言葉を向けられていたそうです。北村さんは子ども心に「卑劣だ」と感じましたが、いまは、その言葉も戦争の過酷な状況が「言わせた言葉」だと考えている、と記事では記されています。
84歳の女性は「婚約者」の墓参りを続けていた…特攻隊員になった彼からの手紙に書かれていたこと
※出典:プレジデントオンライン(2024年10月17日公開)
記事では、84歳だった小栗楓さんの“戦争体験”が紹介されています。楓さんには特攻隊員の婚約者がいました。彼は昭和20年(1945年)に沖縄周辺の海域で戦死を遂げます。2人は小学校の同級生で、出撃の1年前に再会し、それを機に文通が始まりました。甘い言葉は一切なく、求婚の言葉もありませんでしたが、手紙に一度だけ「ワイフと言うものは有難いものだなァ」と書かれていたそうです。<記事を読む>
最後の手紙には「君ありて我れ幸せなりし」と記されており、楓さんは「私が本当に生きたのはその1年間でした」と語っています。遺品として戻ってきた時計と、楓さんが送った銀製の指輪ーー潰れた百合の花の彫刻に、彼の最期が重なります。
楓さんは、役場職員として自らの手で婚約者の戸籍に朱線を引いたそうです。以来、彼女は毎年墓参りを欠かさず、命日にあわせて化粧を整え、祈りを捧げます。
「私たちは、あの人たちのおかげで生かされている。だからこそ、生き抜かねばならない」。過去の戦争がいまも続いているようです。一言では表せない言葉の重みを感じます。
戦争の記憶を風化させないために
終戦から80年が経過しても、埋もれたままになっている戦争の記憶があります。沈黙を貫いた人、語る決意をした人、語る前に亡くなった人。それぞれの「語られなかった戦争」に、いま、少しずつ光が当たり始めています。
その記憶を風化させないために、わたしたちはどう語り継ぎ、どう受け継いでいくべきなのか。本記事がその問いを考える一助となればと願っています。