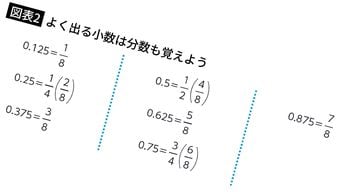反抗期の子供に親はどう向き合えばいいのか。脳内科医の加藤俊徳さんは「反抗してくるのは脳の発達が原因だ。つなぎ留めれば反発され、放任しても不安がられてしまう。難しい時期だが、親には心得ておいてほしいことがある」という――。(第2回)
※本稿は、加藤俊徳『子どもの脳は8タイプ 最新脳科学が教える才能の伸ばし方』(SBクリエイティブ)の一部を再編集したものです。
脳には「得意」「不得意」がある
子どもを見ていると、往々にして「問題」とされる行動のほうが目につきやすいものです。自分自身についても、やはり周囲から問題視されることに、より意識が向きやすいのは無理もありません。
子どもに理解不能なことをされると当惑し、イラつきすら感じてしまう。子どもの能力を伸ばしたいのは山々だけど、どうしたらいいかわからない。思春期を迎えた子どもが、どんどん親である自分から離れていくのが寂しい。かといって、親としてどう接したらいいかわからない。学校や社会で「できないこと」ばかり指摘されて、自己肯定感を削られている。
こうした悩みを解決する一番の鍵は、「脳科学的な理解」です。「問題」とされやすい行動とは、「○○ができない」「こういうときに、○○という困った行動が出やすい」などなど。
しかし、「減点対象」となる特性の裏側には、そういう特性があるからこその「加点対象」があるはずです。すべての人の脳は、得意と不得意の凸凹になっています。どこかが凹へこんでいたら、必ず別のどこかが凸になっている。それが脳というものであり、日ごろ凹みばかりが目につきがちだからこそ、凸の部分を意識的に見出だしていただくことが、本書の目的なのです。