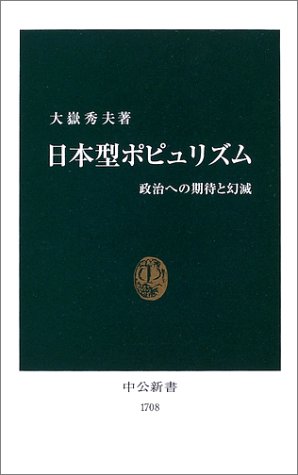ジャーナリスト
東谷 暁
(ひがしたに・さとし)
1953年、山形県生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、編集者に。ビジネス誌や論壇誌「発言者」の編集長を歴任。著書に『エコノミストを格付けする』など多数。
東谷 暁
(ひがしたに・さとし)
1953年、山形県生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、編集者に。ビジネス誌や論壇誌「発言者」の編集長を歴任。著書に『エコノミストを格付けする』など多数。
日本は冷戦終結以後、民主政治の「改革」に邁進してきたが、その改革が何らかの成果をもたらしたと言えるだろうか。まず、ここで民主政治とはいったい何なのか、根本的に考えなおす必要があるだろう。『デモクラシー』(1)は、民主政治という言葉は「万人の情婦」とまで断じた英国の政治学者による辛口の政治学入門。民主政治といわれる政治形態が、必ずしも理想的統治をもたらすわけではないことを、かなりシニックに論じる。
では、民主政治の結果が、しばしば国民を失望させるのはなぜだろうか。それはほかでもない、民主政治が国民の願望を資源として運営される政治制度だからなのだ。『アメリカのデモクラシー』(6)は民主政治を称えた本として紹介されるが、実は、発展途上にあったアメリカの民主政を論じつつ、将来、顕在化する「多数の専制」の危険を洞察した予言の書でもある。
そもそも国民の願望を実現しようとすれば政府が巨大化してしまう。日本でも小沢一郎氏や小泉純一郎氏が改革を説いたとき、官僚を批判して「小さな政府」への転換を主張した。しかし、日本の政府は人口あたりの国家公務員数で見ると先進国中で際立って小さく、中央の官僚が支配しているという説も行政の現実を知れば疑わしくなる。日本の行政および官僚について論じるには、『日本の行政』(8)を読んで初めてその出発点に立ったことになる。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント