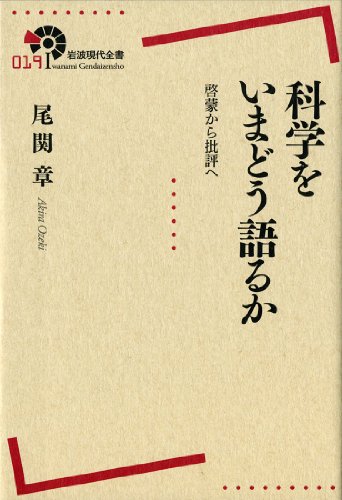遺伝子治療やエネルギー供給を含め、現代社会がかかえる様々な問題に科学は深く関わっている。新聞や雑誌にも特集が組まれるが、どう読み解けばよいのか迷うことが一度ならずある。こうした際に、科学情報を伝えるマスコミの現場を赤裸々に語る好著が出た。著者は朝日新聞で30年以上科学記者を務め、科学医療部長も歴任した「伝える技術」のプロである。何より、歯に衣を着せず本質をえぐり出す文章が心地よい。
全国紙というマスメディアで科学ニュースを伝える記者には、いつも葛藤がある。リアルタイムで問題が発生しつつある科学現場の報道は、知的好奇心のナビゲーター能力だけでは務まらない。ここで著者は、読者にわかりやすく伝えるだけではなく、批評性の高い情報を伝えることが科学報道には不可欠であると説く。本書の副題に「啓蒙からせにつながらない」(99ページ)。これまでの科学者は、フランシス・ベーコンが発した「知識は力なり」という合言葉に従って、ひたすら知識の増加に邁進してきた。ところが、遺伝子操作の威力を知るに至り、人類の幸福とは何かという根本的な問題に直面することとなった。
未来の科学史家は現代を「遺伝子の時代」と呼ぶようになるだろうが、一方では「生命を維持する医療技術が進めば進むほど、世の中ではただ命を延ばすだけの治療に対する疑問が強まった」(89ページ)。実は、医学の進歩が「生命観をさらに深いところで揺さぶる人類史的な問いをはらんでいたにもかかわらず、国内では議論が盛り上がらなかった」(90ページ)という状況が続く。ここに書かれた直言は、地球科学を専門とする評者にも十分インパクトがあり、生命の誕生以来38億年間にわたる「進化」を問い直す契機を与えてくれた。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント