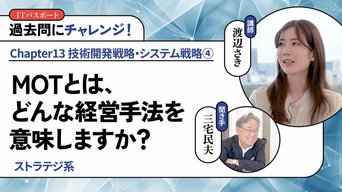厚生労働省によると、2025年3月時点の生活保護の新規申請件数は、2万2484件(前年同月比867件増加、4.0%増)。生活保護を開始した世帯数は、2万395世帯(同1062世帯増加、5.5%増)。賃金は上がらず、物価が異常に高騰する中、さらに生活保護が必要な人々が増えるのは必至な状況だ。
介護や毒親の取材現場で筆者が以前から気になっていたのは、不正受給問題への批判がある中、経済的な困窮者が生活保護を忌避するケースが多いことだった。その背景には、生活保護の仕組みの複雑さや“得体の知れなさ”が影響しているのではないか。そんな問題意識を胸に、かつて生活保護を受給していた方々の話を通じて制度の実態を明らかにして、正しく救われる人や機会を増やしていきたい。
“デキ婚”した夫はDV男だった
関西地方在住の井後史子さん(52歳)は、27歳の時、夫が突然家に帰ってこなくなった。同い年の夫とは、高卒後に入ったバスケットボールの社会人チームで知り合った。交際し、妊娠がわかると、20歳で結婚。21歳で出産した。
エアロビクスのインストラクターをしていた井後さんは、妊娠をきっかけに家庭に入った。夫は高卒後、アルバイトをかけ持ちしながら、ストリートバスケットボールをメインに活動するバスケットプレーヤーだった。
子どもが生まれると、夫に「定職に就いてほしい」と伝えた。渋々と定職に就いた夫だったが、長くは続かなかった。
「母親としての自覚が芽生えた私が、自分そっちのけで家事と育児に追われるのが面白くなかったのか、家族のために定職に就くことでバスケを我慢させられたストレスがあったのかはわかりませんが、夫は毎日のように飲みに行くかギャンブルをするかで、仕事が終わっても真っすぐ帰ってこないようになっていきました」
「もう夫を当てにできない」
当時、夫の給料は現金を手渡しだった。給料が出ると決まって飲みに行ったり、パチンコに行ったりして帰りが遅く、時には数日帰ってこないこともあった。夫の給料が井後さんの手に全く渡らなくなるまで、さほど時間はかからなかった。
たまに帰ってきた夫に、「もう、いいかげんにしてよ!家族のために働いてよ!」と井後さんが声を荒らげると、夫はキレて殴る蹴るの暴力を振るう。井後さんの体にはアザだけが増えていった。
「お酒が入ると気が大きくなる人で、口だけでなく手も出すようになるのですが、お酒が抜けると優しくなる……って、当時はまだあまり知られていなかった言葉だと思いますが、今で言うDVですよね」
多くの場合、DVには、被害者が暴力に怯える「緊張期」、実際に暴力が振るわれる「爆発期」、加害者が謝罪したり優しくなったりする「ハネムーン期(開放期)」という加害者の行動サイクル(周期)があり、何度も繰り返されると言われている。「ハネムーン期(開放期)」で加害者が被害者に優しくなるのは、被害者が自分から完全に離れてしまうのを防ぐためだ。
DVは身体的暴力だけを指す言葉と思われがちだが、精神的暴力(モラルハラスメント)、経済的暴力、性的暴力なども含まれる。井後さんは、経済的暴力も振るわれていたわけだ。
ある日、夫は会社で上司と喧嘩をして辞めて帰ってきた。驚くべきことに、次の職場でも同じことを繰り返し、職を転々とし始めた。当時は保育園が十分ではない時代。「もう夫を当てにできない」と、2歳の息子を預けて働ける託児所付きの仕事を探し、働き始めた。