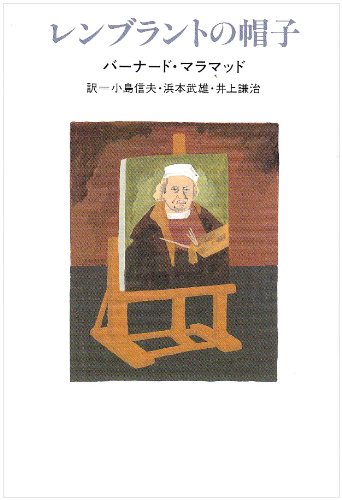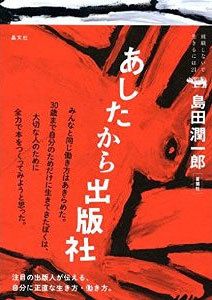最高峰の普通の棚
2013年8月5日、その海文堂書店が閉店するというニュースが、ネット上にあがった。
前々から、厳しいとは聞いていた。『本屋図鑑』の取材のときも、そう聞いた。でも、これだけたくさんの人に愛されているのだから、まだまだ大丈夫だろうと思っていた。殴られたような気持ちだった。
ぼくはニュースの続報をパソコンで検索しながら、「落ちついて考えろ。いま、ぼくになにができるか考えろ」と何度も自分に言い聞かせた。悲しいというより、こんなにも素晴らしい本屋さんがなくなってしまうことへの怒りばかりが頭にのぼった。KさんやHさんたちはどうなってしまうのだろう、と思った。
夜、ドキドキしながら、Hさんに電話をした。ありふれた言葉は絶対に言うまいと思った。
電話に出たHさんは、「ご迷惑をかけて、ほんまにすいません」といつもと変わらぬ明るい口調で言った。
ぼくも「こちらこそ、お忙しいときに、ほんとうにすいません」とできるだけ明るい口調で言った。そして、とにかく一度お店に伺いたいのですが、と続けた。棚が荒れてしまうかもしれない前に、海文堂さんの店内を全部カメラで撮影したいんです、Hさんたちのお仕事を尊敬しているので、とても好きなので、とにかく全部棚を撮影したいんです、と伝えた。
「どうぞ、どうぞ」Hさんはそう言って、それから、声をつまらせて、泣いた。
『本屋図鑑』のイラストを描いてくれた得地さんの旦那さんであり、写真集『多摩川な人々』の著者であるカメラマンのキッチンミノルさんと、翌々日、神戸へ行った。
Hさんたちに簡単に挨拶をし、いつもと同じように冗談をいくつか言って、それから、5時間ほど、店内を撮影した。
やっぱり、どの棚を見ても、素晴らしいのだった。人文書、文芸書、芸術書、児童書、海事書、文庫、新刊棚、どの棚を見ても、海文堂書店で働くひとたちの心が伝わってくるような棚ばかりであった。
ぼくたちが写真を撮っているあいだ、KさんやHさんたちは、棚の補充をしたり、レジに立ったり、注文の本を探したり、電話をとったり、忙しそうに働いていた。見ているこちらの背筋が伸びるくらい、いつもと同じように、テキパキと働いていた。
閉店までの間、海文堂らしい棚をどこまで維持できるか、そこが腕の見せどころだと思っているんですよ。
仕事終わりのKさんは、喫茶店で、そういった内容のことを言った。
海文堂らしい棚とは、派手な棚ではなく、玄人だけがわかる棚ではなく、「最高峰の普通の棚」だと言った。
Kさんは「なくなる書店より、今がんばっている書店さんのところに行ったほうがいいんじゃないですかね」とも言った。
ぼくは、なによりも、海文堂書店のこういう気質が好きなのであった。
キッチンミノルさんとぼくは、Kさんと別れたあと、店の閉店後まで撮影を続けた。棚を撮り、備品を撮り、バックヤードを撮り、レジ閉めをしているHさんや、F店長の姿を撮った。
Hさんがたくさんのスリップを持ってバックヤードへ行くときに、「すごい数ですね」と話しかけた。
F店長が、「昨日、今日と売れているんですよ。ふだんからこうだったらよかったんですけどね」と笑った。
撮った写真をどうするかは、まだ決めていなかった。とにかく、海文堂書店のいまをたくさん撮って、残しておきたかった。
書店は、毎日毎日、変わっていく。一日たりと、同じ棚がある日はない。新しい本が入り、お客さんが買い、書店員たちが並び替え、または返本していく。その積み重ねで、独自の棚ができていく。
「働いている場所と、自分がいちばん好きな場所、両方いっぺんになくなるわけですからね」
喫茶店で、Kさんは、そう言っていた。
「もっともっと、やれたはずなんです」とも言った。
●次回予告
本には元来、読む者の時間を止めるという機能がある。一方、本屋の中には、「時間が止まった棚」があるという。『本屋図鑑』をつくった島田さんは、町の本屋を歩きながらそのことに気づき、考える。次回《時間が止まった棚》。8月25日(日)公開予定。