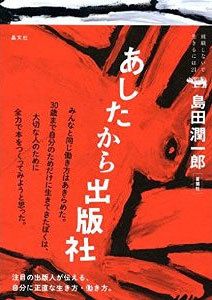たった1人で出版社「夏葉社」を始めた島田さん。だけれども、たった1人で本をつくってきたわけではない。書き手がいて、読み手がいる。その間をつなぐ本屋さんがいる。そうやってこれからも本は読まれていく。
補足しておきたいこと

海に近い本屋さんで、いつも、評論や、社会学などかための文庫本を買っていく、若いお客さんがいると聞いた。
その人は、その本屋さんの棚をじっくりと眺め、なにもいわずに、本をカウンターに置く。もちろん、じっくりと眺めたあげく、なにも買わないときもある。なにを並べたらあのお客さんはもっと満足してくれるのだろう。店で働く人は、品ぞろえについて、もう一度考える。これまでに買ってくれた本のタイトルを思い出しながら、その人の生活にまで、思いをめぐらす。探している本を言ってくれるのなら話は早い。けれど、そういう感じの人ではない。書店員も「なにかお探しですか?」と聞くタイプの人でもない。閉店後、書店員は棚をあれこれといじる。パソコンの前で、発注品について考える。
そして、ある日、講談社学術文庫と、ちくま学芸文庫の棚を、思い切って増やす。小さな田舎の本屋さんなのに、マンガの棚を減らしてまで、品ぞろえを変える。全国の本屋さんを取材して、もっとも心に残ったエピソードのひとつである。
この本を売りたいんだろうな。そういうことが伝わってくる本屋さんが好きだ。そこに並んでいる本は、その店で働く人が売りたい本であり、同時に、常連のお客さんが買ってくれるのではないか、と考えた本でもある。本屋さんの棚は、書店員と、お客さんが一緒につくっている。
だから、ぼくのような部外者が、あの棚はいい、あの棚はよくない、というのは、お門違いというものなのだ。ぼくの好きな棚がある、ということは、ぼくと似たような人が、その店に通っているということである。そうでなければ、単純に、そうでない、という話なのである。
自分好みの店に行くと、買い逃し、すっかり忘れていた本と再会する。または、全然知らなかった、買いたくなるような本に出会う。そういう店が、いちばんいい本屋さん、ということになる。でも、実は、もうちょっと、補足しなければならない。