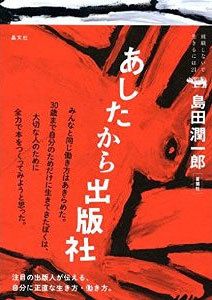「死ぬまで通いたい」
本は、自分の尺度に合うものが、いつだっていいというわけでもない。背伸びしたいときに行くのもまた、本屋さんである。アイロンのかかった、真っ白いシャツを着たような気持ちで、分厚い人文書やら、現代美術の作品集やら、洋書までをも眺める。背筋がピンと伸びる。生活が、洗い清められるような気持ちがする。
肩肘の張らない本が並ぶ本屋さんもまた楽しい。というか、そういう本屋さんへ、いちばん通っている。サッカー雑誌、音楽雑誌、サブカル、マンガ、あまちゃん……。
本屋さんへ行く、ということは、だれかに会うことと同じだと思う。自分と似た人や、尊敬する人。愛する人や、なつかしい人。会いたかった人や、もう会えなくなった人。彼らと、本屋さんを通して、もう一度出会う。
その意味では、本を読むということも、人と会うことと同じだ。たとえば、小説に登場する悪役は、ぼくがもっとも嫌いだった人によく似ている。主人公をいつも助けてくれる素晴らしい人物は、ぼくが尊敬する素晴らしい友人のようで、魅力的なヒロインは、ぼく好きだった女性のことをどこか思わせる。本を読むということは、知らなかったことを知るということであり、忘れていたいろんな記憶を思い出すということでもある。
本は、あらゆる場所と、人とに、つながっている。携帯電話や、インターネットとは違い、抽象的に、控えめに、つながっている。本屋さんもまた、抽象的に、控えめに、あらゆる場所と、人とに、つながっている。
ぼくが全国の本屋さんをまわり、真っ先に感じたのは、なつかしさであった。懐古主義というのではない。しばらく会っていなかった人に会ったような、喜びともいえる、なつかしさだった。日本には、そうした本屋さんがたくさんある。
ぼくは、町の本屋さんが好きだ。大きな本屋さんも、小さな本屋さんも、個性的な本屋さんも、そうでない本屋さんも、全部好きだ。死ぬまで通いたい。そのために、できることをやりたい。
追伸
『本屋図鑑』の取材で感銘をうけた書店のひとつが、栃木市にある出井書店であった。
記事を担当した空犬さんは、この本屋さんで出会った女性のことを、こう書いた。
「店頭に立つ長谷川千子(せんこ)さんは大正生まれ。『お客さんに迷惑をかけないように』、それだけを考えて、昭和八年から店頭に立ってきた。昔は、小柄な長谷川さんが、神田村まで自ら買い出しに行き、重い本を背負って帰ったという。」
その長谷川さんが、今年の6月に亡くなられた。
楽しそうに話されていた姿を思い出す。
80年もの間、本屋さんに立ってらっしゃった。
ご冥福をお祈りいたします。