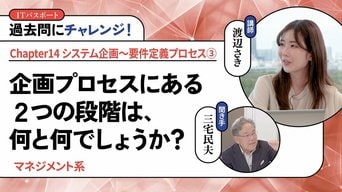※本稿は、片田珠美『マウントを取らずにはいられない人』(PHP研究所)の一部を再編集したものです。
理不尽な異動を強要する“学長の暴走”
名門国立大学の教授を定年退官した60代の男性は、某私立大学の学長に就任した直後、ドイツ語の哲学書を買うよう要求し、購入リストを一緒に連れてきた弟子に作成させた。しかし、図書館の責任者を務めていた40代の女性は、学長から渡された購入リストに記載されていたドイツ語の哲学書をすべて購入するわけにはいかない旨を伝えた。
すると、学長は「何を抜かすか!」と激怒した。そして、事務長を呼びつけ、図書館の責任者を庶務課に異動させた。この責任者は図書館司書の資格を持っていたにもかかわらず、まったく関係のない部署に飛ばされたのである。
図書館の責任者が購入リストに記載されていたドイツ語の哲学書をすべて購入するわけにはいかない旨を伝えた背景には、切羽詰まった事情があったようだ。この大学は毎年定員割れしており、図書購入の予算が元々少なかったうえ、責任者は一層の削減を理事長から言い渡されていた。理事長からの指示に従わないわけにはいかなかったのだ。
そのため、責任者はドイツ語の哲学書の購入にそれほど多くの予算を割けない理由について「うちの大学は、中学生レベルの英語の本も満足に読めないような学生さんばかりなので、ドイツ語の本、しかも難しい哲学の本を読める学生さんはほとんどいないと思います。ですから、うちの大学のレベルに合った本を購入したほうが、学生さんのためになるのではないでしょうか」と説明した。
責任者の対応は至極まっとうなように私の目には映る。名門国立大学のように図書購入の予算が潤沢なわけではないのだから、学生がより必要としている図書を優先的に購入するのは当然だろう。読むのが学長とその弟子くらいしかいないドイツ語の哲学書の購入の優先順位が、多くの学生にとって必要な入門書や参考書などよりも低くなるのは当然だと私は思う。
怒りは自己に対する過大評価から生まれる
だが、学長にとっては受け入れ難かったようで、「私がこの大学の学長になったからには、東大や京大に匹敵するほどの名門大学にするつもりだ。その一環として、戦前の旧制高校の教養教育を復活させたいと思っている。そのためにも、ドイツ語の哲学書は必要なんだ!」と怒鳴った。
ここまでドイツ語の哲学書に学長がこだわったのは、学者としての矜恃によるところが大きい。ドイツ哲学の研究者として有名だった学長は、「ドイツ留学中にハイデッガーに直接会ったことがある」のが自慢で、教授会でもその話を持ち出すくらいだから、ドイツ哲学へのこだわりは半端ではなかった。
だからこそ、学長が希望したドイツ語の哲学書をすべて購入するわけにはいかないと伝えた図書館の責任者に対して激怒し、まったく関係のない部署への異動を強要したのだ。
この怒りを生み出したのは、古代ローマの哲学者セネカが見抜いたように、学長の「己に対する過大評価」(『怒りについて 他二篇』)にほかならない。名門国立大学で教授を務めたほどの立派な学者で、ハイデッガーに直接会ったこともある自分に逆らうとは何事かというわけだ。
しかも、自分は学長であり、この大学のトップを務めているのだから、その要求すべてに職員が応じるのは当然との認識もあったように見受けられる。要するに、名門国立大学で積み重ねた経歴も研究業績も、私立大学で手にした肩書もすべて「過大評価」しているからこそ、少しでも思い通りにならないことがあると激怒する。
おまけに、やはりセネカが指摘したように「怒りとは罰を科すことへの欲望」(同書)なので、自分の要求に応じず、不快な感情をかき立てた相手にできるだけ重い罰を与えようとする。普通の人なら、そんな重い罰を与えることはできないが、学長という立場上それができるので、図書館司書の資格を持つ女性にまったく関係のない部署への異動を強要した。