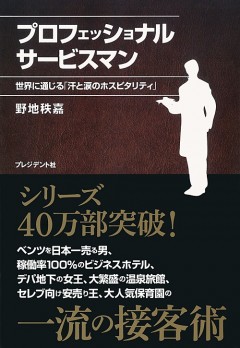「河野、どうだった? 今日の日報を出せ」
それで、素直に日報を書いて、係長の机の前に持っていくと、「おう、河野。ここにある桜ヶ丘1丁目の小林さんはどんな人だ」と尋ねられる。答えに言いよどんだりしようものなら、「お前、嘘を書いたな」と追及されるのである。
現在、ヤナセ世田谷店の副店長を勤める河野敬さん(47歳)は、19年の間にメルセデスベンツだけで1530台を売りまくり、文字通り「日本一メルセデス・ベンツを売る男」と言われている。その彼も、新人時代はノルマが達成できず、上司に怒られる毎日が続いていた。
マエダ係長は部下が報告書をでっち上げたかどうかを厳しくチェックしたが、新人がベンツを売ってこなかったからといって怒ることはしなかった。売れるに越したことはないが、新人にはそこまで期待していなかったのである。飛び込み営業の厳しさは上司としてよくわかっていたから、結果追求よりも、セールスマンをきたえる教育の一環と思っていた。
当時もいまもヤナセでは、新人には飛び込み営業をさせる。その際、上司や先輩は次のような鉄則を叩き込み、加えて標語を覚えさせる。ベンツやBMWを売っているわけだから、一見、スマートな社風のように感じられるが、ヤナセは泥臭い営業を信奉する会社なのである。
上司、先輩は「テリトリーに着いたら、軒並みベルを鳴らせ」と鉄則を語る。
「なぜ、軒並み訪問なのか。お前が家の構えを見て、あそこは買わないだろうと判断すれば、飛ばしてしまう。隣もダメだと思えば2軒飛ばす。そのうちに10軒の家を飛ばし、しまいには100軒を飛ばすようになる。
いいか、買う買わないを決めるのはお前じゃないんだ。お客さんが決めるんだ。ダメと決めつけることをせず、とにかく軒並み、回る癖をつけること」
そして、営業に出かける前の新人にはふたつの飛び込み営業の真髄を唱えさせて、くぎを刺す。
「効率とは怠け者の言い訳」
「帰ろうと思う前にもう1軒」
新入社員だった河野もふたつの言葉をぶつぶつとつぶやきながら、ベルを押しては、「結構です」と追い返され、「河野と申します」と挨拶しては「だから、どうかしたの」と鼻であしらわれた。それが、6月、7月と続いた。社会人になって初めて買ったスーツは汗にまみれ、ネクタイからは塩がふいた。
昼食の後はなかなか営業に回る気になれず、喫茶店で時間をつぶす金もなく、公園のベンチで横になるようになった。しかし、それでも、最低、100軒は歩いて回ると決めたから、毎日、ベルを押した。けれども、まったく売れなかった。売れる気配すらなかった。
※この連載は『プロフェッショナルサービスマン』(野地秩嘉著、プレジデント社)からの抜粋です。