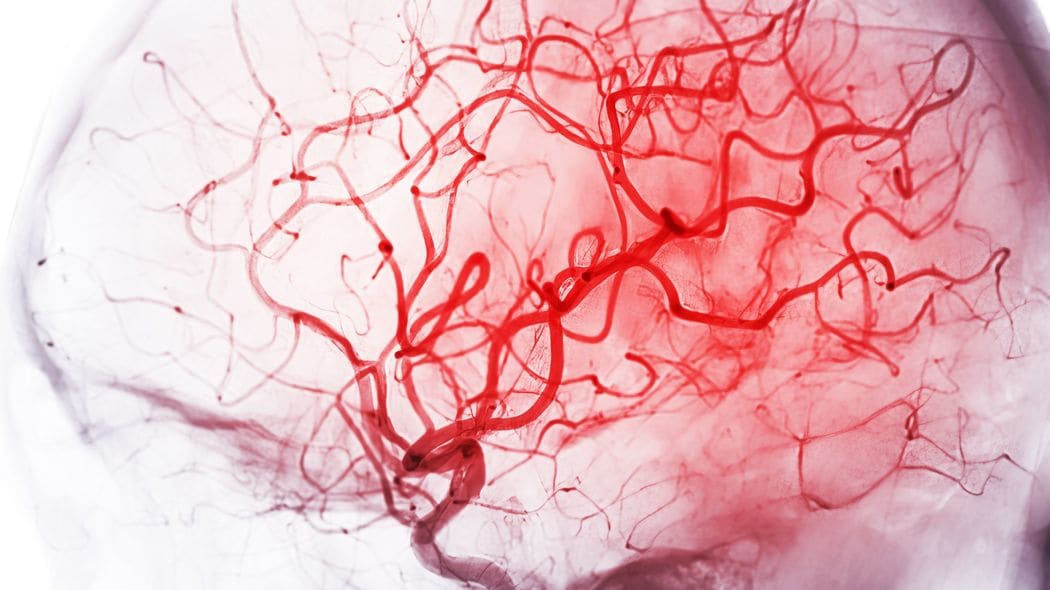母親の号泣
7歳上の夫が「進行性核上性麻痺」という不治の病にかかった関西地方在住の久保田悦子さん(仮名・現在67歳)。医師によってそう診断された2020年2月頃、87歳の母親が一人暮らしをする実家の隣に住んでいる妹(54歳)から電話がかかってきた。
母親が歩行器を使って買い物に出た帰りに転倒して左腕を複雑骨折し、救急車で運ばれたという。
母親は80歳の頃に肺がんと診断されている。そのため、骨折で搬送された先の病院から「肺がんでかかっている総合病院で診てもらってください」と言われ、「お姉ちゃんも一緒に来てほしい」という内容だった。
久保田さんの家から実家までは自転車で30分くらい。母親がかかっている病院は、実家からタクシーで10分くらいの場所にあった。
久保田さんは、妹と一緒に医師の話を聞いた。
「医師の話は非常に冷酷なものでした。『複雑骨折のため、骨がグチャグチャになっている。手術するとしたら、何時間もかかる大手術になるが、(治療中の)肺がんがあるため命の保証ができない。腕をとるか命をとるかの賭けになりますが、それでも手術しますか?』と言われました。最初に肺がんと言われたのが何歳だったのかよく覚えていないのですが、手術も抗がん剤も、一切の治療を母が拒否したことははっきりと覚えています。日頃から母は、『長生きし過ぎた』と口癖のように言っていました」
だから久保田さんと妹は、手術を受けないことを選択した。
「『もう骨はくっつきません。腕は動きません。一生、三角巾で腕を吊って暮らしてもらいます』と言われてそのまま帰りました。母はかなり足が弱っていて、歩行器を使っていたものの、一人暮らししていました。実家の近くのガタガタの狭い路地で転倒して動けなくなっていたところを、郵便配達のおじさんが見つけてくれて、家まで背負って連れてきてくれたそうです」
左腕の骨折の後、母親は起き上がることすらできなくなり、寝たきりになってしまった。
長屋の隣に住む妹が毎日3食運び、オムツを替え、身体を拭いてやるようになった。
母親が寝たきりになる前、久保田さんはほとんど実家に顔を出していなかったが、「とにかくまずは、介護ベッドが入るようにしなければ」と、ゴミ屋敷状態になっている実家を片付けるために、週2回ほど通うように。
実家はもう履かないであろう靴や着ないであろう服など、不要と思われるもので溢れ、足の踏み場もないほどだった。
ある日、久保田さんと妹が実家を片付けていると、隣の部屋から「ウオー! ウオー!」という声が聞こえてきた。母親の声だ。
「お姉ちゃん! お母さんが変!」妹が慌てて隣の部屋に行くと、
「お姉ちゃん、お母さん、泣いてるわ」と妹。
母親は「世話かけてごめん」と言いながら、「ウオー! ウオー!」と大声をあげて泣いていた。
久保田さんは母親を抱きしめながら、
「大丈夫。泣かなくていいから。私らが赤ちゃんのとき、おむつ替えてくれたでしょ。親子なんだから、心配しなくていいから」
と言い聞かせていると、いつの間にか久保田さん自身も泣いていた。
妹は「息ができなくなったかと思って心配したんだから」とブツブツ言いながら、呆然と立ちつくしていた。
久保田さんは夫(当時68歳)の介助もあるため、長時間家を空けることができない。
デイサービスを申し込み、入浴させてあげたいと考えていたが、当時はコロナ禍。新規で受け付けてくれる施設はなし。基本、母親の身体的介護は妹がやっていた。