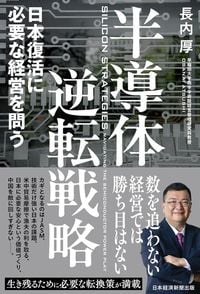いまこそ松下幸之助氏の水道哲学を思い出すべき時
日本の場合は、投資すべき段階で大きく投資をせず、次の技術に行ってしまうので、結局は台湾や中国や韓国の、都合のよい実験場にされてしまうのです。
台湾メーカーの発言を聞いて、経営の神様と呼ばれた松下幸之助氏の言葉を思い出しました。パナソニックは2008年にこの社名を変更しましたが、それ以前は松下電器産業と言いました。その松下電器産業をもじってマネシタ電器と言われていた時代があったのですが、それは、二匹目のドジョウ戦略というか、他社から新製品が出るのを待って、同様の商品をつくり市場に大量に供給したことから付けられたあだ名なのです。
創業者の松下幸之助氏は当時、「我々は東京にソニーという研究所を持っている」と言ったことがあるのです。つまり、新しいものを試行錯誤しながらつくるのはソニーに任せて、それが完成したらパナソニックがソニー以上に大量につくって安価にし、大量に市場に投入する。幸之助氏独自の水道哲学がまさにこれなのです。商品を水のように安い価格で誰もが手にできるものにするという発想なのです。
幸之助氏の「ソニーという研究所を持っている」という発言は、開き直りのようにも聞こえますが、恐らくそうではなく、開発の順序が1番手か2番手かということはそれほど重要ではなく、数において1番手か2番手かということのほうが社会的意義は極めて大きいということを理解していたからではないでしょうか。
しかし最近は、パナソニックがソニーのような企業になってしまっているのです。創業者の残した水道哲学が伝承されることなく消えてしまったことが、パナソニックの一番の問題点だと思います。
新しいことはやらなければなりません、脱成熟に備えるために。しかし、成熟化のタイミングではしっかりと数を追わなければいけないのです。水道哲学こそ21世紀に応用しなければならないのに、それができていないところが、パナソニックの非常に大きな問題点だと思っています。