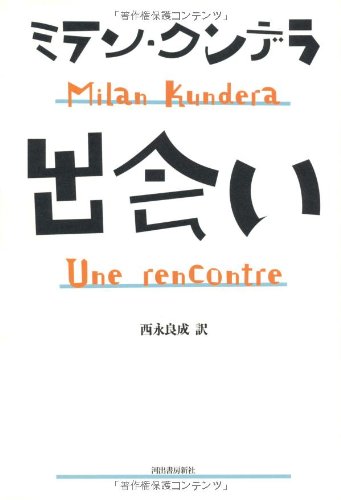科学技術の驚異的な発展が豊かさをもたらした20世紀は、一方で、歴史上に例を見ない規模の戦争や虐殺が暴発した時代でもある。その過程で、人々が疑問もなく受け入れていた感情や、人を愛するといった基本的なこと、生きるかたちそのものを根底から崩壊させてしまった。その象徴が「文化や芸術、その歴史が世界のモデル」という矜持のあったヨーロッパの崩壊である。神や、人間の矜持を失い、人生が「意味のない偶発事」となってしまったときに、どのように生きるための理由を見つけるのか。本書の視線はそこにある。
クセナキスという極めて難解な現代音楽家がいた。「プラハの春」がロシアの戦車に踏みにじられ、チェコスロヴァキアが占領されたとき、「ロシア帝国の内側では、他の多くの国民が自らのアイデンティティまで喪失しようとしていた。そこで私は(中略)明白なことを理解したのである。チェコ国民は不滅でなく、存在しなくなることもありうるのだと」。クンデラのクセナキスの音楽への愛着は、そんな時代を背景としている。
クセナキスの音楽とは、端的にいえば文化・芸術の頂点ともいえるヨーロッパ音楽に背を向けるものである。ヨーロッパ音楽は、ひとつの音符にひとつの音階という人為的な音に基づいており、そこには人間の主観性が表現されている。しかしクセナキスの音楽は、心の内面からわき出る主観の表現ではなく、騒音や雑音といった、外界にある客観的な音を出発点とする。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント