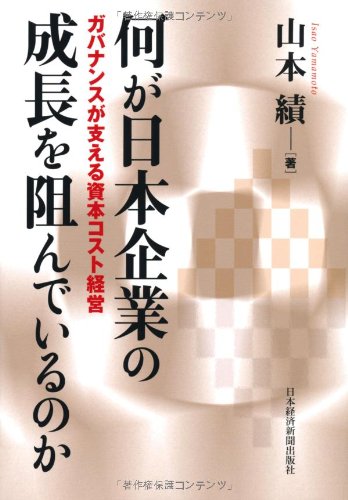ずっと気になっていたことがあった。本書に何度も出てきた「株主全体の目線」という言葉である。例えば、こんな具合だ。「株主を基軸とする経営とは、個々の株主の目先的な欲得に迎合することではない。『こう考えるはずだ』『こう期待するはずだ』といった株主全体の目線を想定して経営を行えば、他の利害関係者が犠牲になることなしに株主価値を高めることができる」。
別書『株式投資家が会社に知って欲しいこと』(日本コーポレート・ガバナンス・フォーラム編、商事法務)では、こうだ。「よく企業経営者と会って話をさせて頂くと、時々、『株主の顔が見えないから、誰を向いて経営に関する説明責任を果たすべきなのかわからない』という声を耳にします。…(中略)…顔の見えない株主の平均的な意向は何でしょうか。それがコーポレート・ファイナンス(企業の資金調達・運用)なのです」。
この二例を総合すると、「株主全体の目線」=「株主の平均的な意向」=「コーポレート・ファイナンス」となる。日本の企業経営者は、株主という個別具体的な、すなわち人間のような存在をイメージしがちであるが、実は、株主とはかなり抽象的な「論理の体系」だといえる。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント