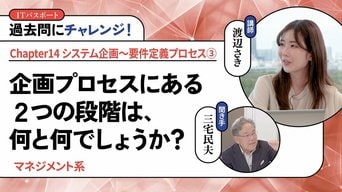史実の小泉八雲は“身構えてしまうような人物”
NHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」第13週は、朝の番組とは思えない修羅場回。月照寺でヘブン(トミー・バストウ)とイライザ(シャーロット・ケイト・フォックス)と錦織(吉沢亮)が、トキ(髙石あかり)と銀二郎(寛一郎)にバッタリ出くわしてしまう。
そのまま参道の石畳の上で始まる自己紹介。錦織は空気読まずに、銀二郎はトキの前の夫で〜、私の古い友人で〜と紹介。さらにイライザが、英語でトキに「じゃあ、あなたがヘブンの話していた、おっちょこちょいの女中ね」なんて言葉まで、そのまま通訳。ヘブンにまで「全部訳さなくていいから」とたしなめられることに。
全員が微妙なまま進む、ぎこちない会話にいったいどうすればいいのか。ただ、よくわかったのは、ヘブンがけっこうモテモテということだ。
演じているバストウが長身のイケメンなので誤解してしまうが、正直、八雲は正反対の人物だ。

身長も低く奇妙な歩き方をするし、近眼なので話をするときにやたらと距離が近くなる。おまけに神経質ですぐに感情が高ぶる。いわば、すぐに不機嫌になってキレる面倒くさい男である。ぶっちゃけ「作家です」という看板がなければ、ちょっと身構えてしまうような人物である。
しかも、作家としても取材しているのはスラム街だとか、クレオール文化。現代でいえば『実話ナックルズ』とか『実話BUNKAタブー』あたりでいつも見かけるライター、コアな読者には読まれても、世間は微妙……といった感じである。
八雲の長男「冷血漢とさえ思われるほどに真剣」
作中でもイライザは、トキの怪談に執拗にくいつくヘブンに才能を認めながらも、ちょっと呆れた雰囲気。作家としての才能がなければ「なにこの人、きっしょ……」となってもおかしくない。
だから、史実の八雲は女性にキモ悪がられていたんだろうな……と思いきや、違う。意外にも八雲はアメリカ時代からけっこうモテていた。
長男一雄の『父小泉八雲』(小山書店1950年)には、西インド諸島に長期滞在した時の、女性との逸話を始め、いくつもの女性とのエピソードが記されている。そのいずれも、熱をあげているのは女性のほうで、八雲はそれを迷惑がって距離をおいたようにみえる。
いったいこれはどういうことなのだろう。
八雲に惹かれた女性達が感じたのは「この人は真剣に私だけを見ていてくれる!」という勘違いだったのだろう。八雲は根っからの取材者である。作中では、ヘブンがトキに距離を詰めて怪談を聞いているが、あんなものではない。長男・一雄は、八雲が記者として駆け出しの頃、血なまぐさい殺人事件を好んで追いかけて新聞紙上で好評を博したことを、こう語っている。