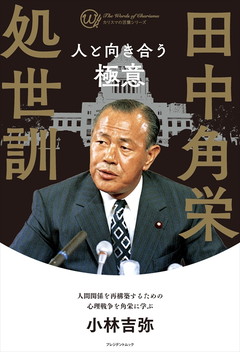「カネは受け取るほうがどれだけ心に負担となっているか、他言されたらどれだけ恥ずかしいか、その辺が分からんでカネが切れるかだ」
まさに、前項の「そこが分かって一人前」ということである。生きたカネは、やがて“芽”を出すことを知っておきたい。敵も、味方になるということである。
招かれていないのに……葬式に駆け付けるワケ
とくに重視したいのは葬祭だ。
結婚式などは
皆が喜んでいるのに対し、
葬式は誰もが落ち込んでいる。
寄り添ってやるのは
当然のことではないか。
田中は、情にもろい男であった。そのために「“情と利”の角さん」などとも言われていた。結婚式などめでたい席は、みんなが喜び祝福をしているので、どうしても出席しなければならないということはない。むしろ、人々が悲しんでいる葬式にできるだけ顔を出し、遺族に慰めの言葉でもかけるべきだとする姿勢を通したのである。
実際、田中は人の不幸には居ても立ってもいられず、葬式に駆け付け、遺族と一緒に涙し、激励するという光景をあちこちで見せている。
象徴的なエピソードがある。田中が幹事長時代の1965(昭和40)年、かつての政敵であった社会党の元委員長・河上丈太郎の訃報を聞いた田中は、社会党、河上家のどちらからも招かれていないのに葬儀に駆け付けたのである。年末の雨の降る寒い日である。
田中は2時間ほど立ち尽くし、野辺の送りをやった。足元は雨が跳ね返っていた。
河上とは、自民党と社会党の対立時代が始まった「55年体制」のなかで、激しくやり合った仲であった。そんな田中が葬儀にわざわざやって来た。自民党から参列した幹部は田中一人であった。葬儀に参列した社会党議員らから、「田中というのは凄い男だ」という声が漏れ聞こえてきたものだった。
また、予定をすべてキャンセルして葬儀に駆け付けたり、時間がなくヘリコプターを飛ばしたりして駆け付けたということもあったのである。
そうした田中の姿勢は、のちにいろいろな政治の局面で生きることになる。社会党とは、国会で日韓条約や、学生運動に対する大学法案などで何度もわたり合ったが、初めは突っ張っていた社会党も、やがて「田中が言うなら仕方がない」となり、落としどころを見つけて妥協する場面も少なくなかったのだった。「55年体制」下、田中がスムーズな国会運営に果たした役割は大きかったのである。
宴会に顔を出し、膝を折って語らう
嫌われる。
膝を折って
自ら酒を注ぎ、
話をしてこそ、
人から喜ばれる。
田中角栄は首相になる前の大蔵大臣、自民党幹事長、通産大臣時代を通じて、じつにマメに宴席に顔を出していた。政界の実力者、加えて庶民派として国民の人気も抜群だっただけに、中央政界の中堅・若手議員、財界、地方議員、中小の事業家など、「先生のお話を聞きたい」と“宴席出席要請”が途切れることがなかったのだ。