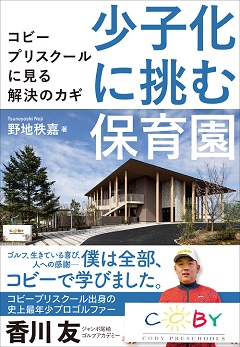※本稿は、野地秩嘉『少子化に挑む保育園』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。
1歳の娘に「先生」と呼ばせるのがつらかった
コビープリスクールはこざきの園長をしている水城智恵は、小林照男代表の母、典子が教えた保育士だ。その頃、30歳だった水城は運営受託した園の保育主任になった。主任になったのは典子が始めたマトリクス保育など、コビーの保育スタイルを指導する役目を負っていたからだ。
彼女は言う。
「直前まで、別の保育園で働いていました。小林代表から『新しい園に来てくれないか』と声がかかったのです。私としてはありがたいと思いました。新しいことに挑戦したいなと思っていた時期でしたから。
もうひとつ、理由があります。それは子どものことでした。当時、私は結婚していました。子どもは1歳の女の子です。勤め先の保育園に連れてきて、保育してもらいながら、自分は他のクラスで担任をしていました。
朝、出かける時、1歳の娘に『いい、園に行ったら先生と呼ぶんだよ』と言わなきゃいけなかった。娘はうちでは私のことを『かあたん』と呼んでいました。でも、園では先生と呼ばなければいけない。1歳の娘にそんなことを言うのはあまりにかわいそうで……。
そんな状況に耐えられなかったので、コビーが複数の園を持つのであれば、ひとつの園に預けて、私自身は他の園で働くことができます。それで、移ることにしたんです」
「余計なことはしない」のが公立の保育だった
水城が話したことは子どもを持つ保育士であれば誰もが経験することだ。自宅近所の園に勤務できた場合、自分の子どもを同じ園に入れることがある。ただ、自分で保育することはない。子どもが4歳、5歳であれば状況を理解するだろう。しかし、1歳児、2歳児に「お母さんと呼ぶな」は酷だ。水城が小林の新しい園に飛びつくように転職したのもうなずける。
だが、水城は転職して驚いた。当時の野田市ではコビーほどの丁寧な保育は行われていなかったのである。
「私はあたご保育所に勤務させていただきました。当初はコビーらしさを取り入れることができず、園長先生(小林わか子)と相談しながら、少しずつ新しい保育、コビーらしさを取り入れていく感じでした。
びっくりしたのは折り紙を折って飾りをつくる『お製作』をやっていなかったこと。公立の保育園では、子どもを預かったら、面倒を見ることだけが保育でした。それが長年続いていたのです。私たちが『お製作』や七夕のための竹取りなどを始めたら、保護者からクレームが入るんです。
『余計なことをするな。あんたたちはただ、子どもの面倒を見ていればいいんだ』と」