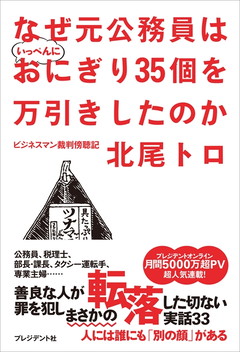「将来は介護関係、復興支援の仕事に就こうと考えています」
今後どうするつもりかと尋ねられた被告人の、空疎な予定が法廷内に響く。
「将来は介護関係、復興支援の仕事に就こうと考えています。それで少しずつでも。あと、フィリピンの資産が……あの家は私のものですから、あれが入れば全額弁償に充てます」
1961年生まれの被告人は高校卒業後、楽器業界に入った。将来社長になるなど思ってもみなかっただろう。ところが前社長に見込まれ、30代後半で会社を譲り受ける。
7000万円の家を海外に持ったくらいだから、途中までは羽振りも良かった。思いがけず手にした社長の椅子や経営権。それが人生のピークをもたらしてくれたのだ。
しかし、金銭的余裕は被告人からコツコツ頑張る意欲を奪い、過信を芽生えさせたに違いない。会社が好調だったのは、前社長の時代に培った信用が土台にあったからなのに、自分の経営手腕によるものだと錯覚したのかもしれない。
高い家賃がネックのひとつだとわかっていながら最後まで規模を縮小しなかったのも、潔く会社を畳んで自己破産しなかったのも、この苦境を乗り越えられればまたいい時代がくるという甘い見積もりがあったからではなかったか。フィリピンの家を処分しようとした形跡は一度もないみたいだし。
価値ある楽器を預かり、売りさばいた後に支払うシステムだったため、目先の金に目がくらんで起こしたように見えるこの事件。でも、そうなる兆しは、社長の器ではない人間がトップに就き、信用という会社の財産を食いつぶしながら贅沢な暮らしをしている時期に生じていた気がする。
社長と呼ばれる快感、高額の楽器を持つ金持ちから頼られる喜び、海外に資産を持っている満足感、落ちぶれたと思われたくない見栄……。被告人は結局、自分の中にある“強すぎる欲望”に負けたのだと思う。